お客様の継続利用率95%の実績 DX開発に関する高品質のオフショア
ベトナムのトップ理系大学を卒業した400名以上の経験豊富なIT技術者と、ビジネス日本語に精通したブリッジSEを擁するHBLABは、お客様に安価かつ高品質なサービスをご提供し、DX成功に向けてサポートします。
ソリューション

小売業向けソリューション
- ネットスーパー・EC
- 在庫管理
- 顧客管理 (CRM)・ポイント管理

ERP ソリューション
- 経費システム
- HRシステム
- SAP
- Odooビジネス

金融業向けソリューション
- カード系
- 保険系
- 決済関連系

デジタルマーケティング
- EC関連
- SaaS型・オンラインサービス開発
- エンタープライズ(CRM関連)

先進テクノロジー
- Blockchain
- AR/VR
- AI・人工知能

オフショア開発
- Web・アプリ開発
- 業務系システム開発
- テスティング
- マイグレーション・インフラ構築
実績
事業概要:管理システム/決済システムの開発と改良
日本で多数の小売の代理店を持っている企業様
事業概要:管理システム/決済システムの開発と改良
小売代理店の運用向けに、在庫確認、店舗間の価格と購買力の比較、製品販売数の予測、商品カテゴリごとの販売データ集計などの機能を有する管理システムを構築しました。 また、決済アプリ制作とカードでの支払い機能によって、決済の利便性向上、現金支払いの削減、キャッシュレス化を実現しました。マニュアル操作がなくなり、使いやすさが改善しました。
詳細
事業概要:オールインワンのマーケティングシステム
マーケティング・ソリューション提供会社様
事業概要:オールインワンのマーケティングシステム
中小企業、スタートアップ、フリーランサーに向けに、Webサイトとセールスファネル作成を含むオールインワンのマーケティングシステムを提供しました。 セールスファネルのステージに基づき、メールマーケティング自動化システム、ランディングページの決済機能、アフィリエイト管理機能などを開発しました。導入後、エンドユーザーからの高評価をいただきました。
詳細
事業概要:健康保険証の情報抽出
事業運営、会計・財務管理、及び不動産サービスを提供する日本の大手企業様
事業概要:健康保険証の情報抽出
情報入力にかかる時間・人員コストを減らし、人為的ミスが発生するリスクを避けるため、より速く、正確で、コスト削減が可能な収集のAIモデルを提供しました。AIモデルの組み合わせによって、ロゴと店舗名の精度は93%、他の情報の精度は95%〜97%達します。その結果、初期のデータ入力の工数を20%削減し、コストと作業速度を最適化しました。
詳細
事業概要:勤怠管理システムの改良
勤怠管理システムを提供しているソフトウェア開発会社様
事業概要:勤怠管理システムの改良
ユーザーがより簡単に操作できるように、アカウント1つでWebでもアプリでもログインできるSingle-Sign-Onシステム機能を搭載したシステムを開発しました。休暇申請や休日・休日の表示、勤務時間の分析などの機能の改善・開発も行っています。 管理するデータ アカウントの数が減り、異なる管理プラットフォームで従業員の活動を同時に管理できるようになりました。
詳細
事業概要:おもちゃの通販サイト
子供向けのおもちゃや本の販売会社様
事業概要:おもちゃの通販サイト
製品の特性に合わせてアイテム分類、サブオーダー管理などの追加機能をカスタマイズし、EC-CUBEでオンライン販売システムを構築しました。新規サイトを運用した後、200万人以上のユーザーのニーズを満たし、収益化に向けての速度を上げ、運用コストを最適化できるように支援しました。
詳細
事業概要:AIによる中古車価格推定
ソフトウェア開発会社様
事業概要:AIによる中古車価格推定
市場に出回っている30万以上の同様の製品の仕様に基づいて、写真から自動的に情報を分析・入力するAIの技術を用いたソリューションでユーザーエクスペリエンスを最適化します。モデルを使用することで、250車種のメーカー、色、モデル、製造年に関する情報を最大95%の精度で自動入力されます。表示価格は情報の正確性と車両価格の分類に応じて、誤差を最大20,000円まで抑えることができます。
詳細
事業概要:金融情報管理サイト
日本金融業界の大手企業様
事業概要:金融情報管理サイト
企業とエンドユーザー双方のアカウント登録、情報更新・検索、借り手と取引の情報の検索と取得などの機能を備えた新しいWebサイトを構築しました。新規サイトを運用した後、請求書検索・取得の時間と労力を削減し、大量のデータからの検索性が向上し、対応もスピーディとなりました。
詳細
事業概要:経費精算システム構築
ソフトウェア開発会社様
事業概要:経費精算システム構築
営業活動を強化する過程で、セールスの出張などの費用、管理者・経理担当者・セールスの手間を削減するため、決済前・後の申請書作成、自動で総額を確認・計算、上長への提出・承認、経理部の確認後支払いなどの機能を備えたシステムを開発ました。導入後、マニュアルの登録から承認までの時間を削減し、事業をスムーズに進めることができます。
詳細
なぜ HBLAB?
0
+
プロジェクト
0
+
メンバー
0
%
日本語コミュニケーション可能
0
%
お客様の継続率
お取引先企業
お客様インタビュー
今回は、実際に弊社と共にオフショア開発を行い、書店にビデオ通話付きマッチング機能を追加した「Chaptersbookstore」を開発、Mission Romantic社 代表取締役の森本萌乃 様にお話を伺いました。 構想からビジネス特許獲得に至るまでのオフショア開発エピソードを、弊社のベトナム現地エンジニアの感想も交えて丸ごとご紹介します。
詳細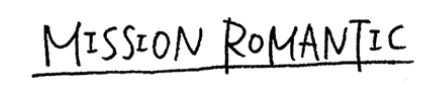
今回は、弊社HBLABが共同開発したサービスについて、エキサイトの岡野様とワンオブゼムの武石様にインタビューしました。 どういった経緯で弊社HBLABにご依頼いただいたのか、また、HBLABとの共同開発において良かったこと悪かったことをせきららに語っていただきました。
詳細
今回は、弊社とともにオフショアでECサイト開発を行った、遠鉄システムサービス株式会社のプロジェクトマネージャー、鈴木様と乗松様にお話を伺いました。 構想からリリースに至るまで、オフショア開発のエピソードをご紹介します。
詳細
今回は、弊社ラボ型開発サービスを獣医師、および獣医療企業に対する情報サービスに適用して構築推進をリードした、株式会社Zpeerのチーフエンジニアの方にお話を伺いました。 ラボ型開発で開発チームの増強をどのように最適化進めたのか、本実例を参考にしていただければ、幸いです。
詳細
Previous
Next
お問い合わせ
個人情報の取扱いに関する確認事項を必ずお読みの上、お問い合わせ下さい。※は必須入力項目です。