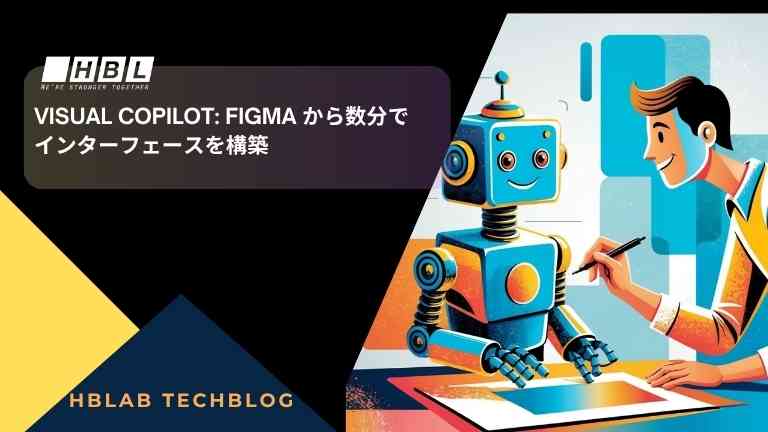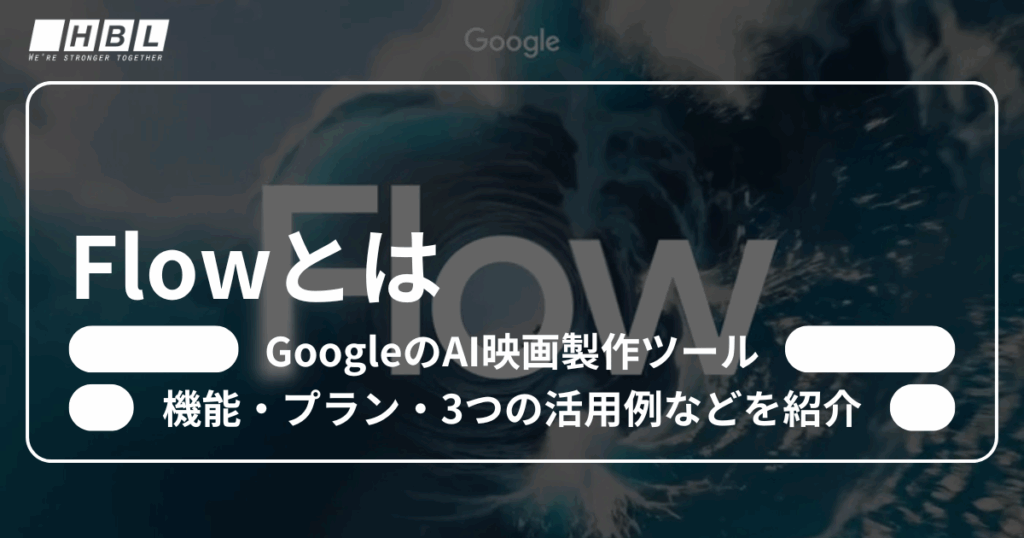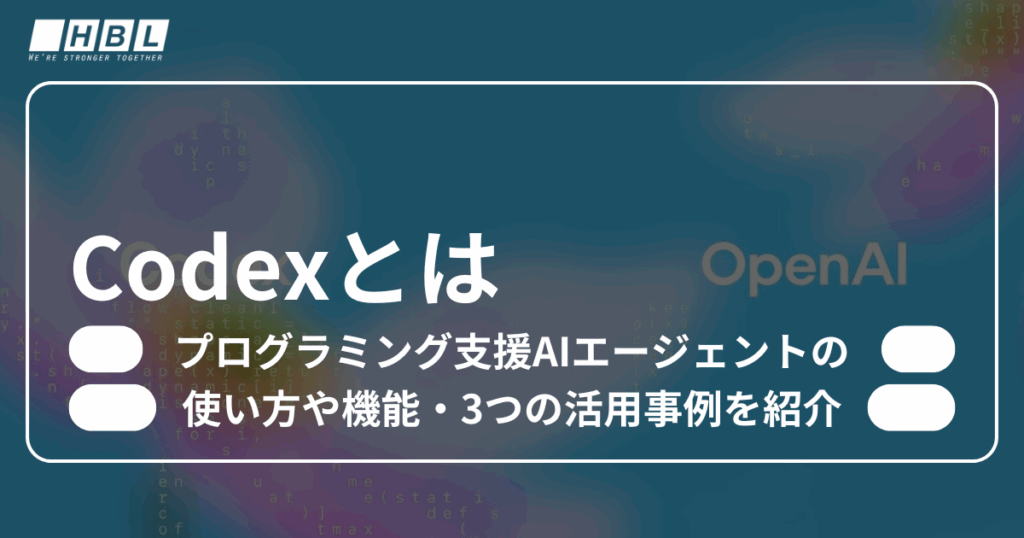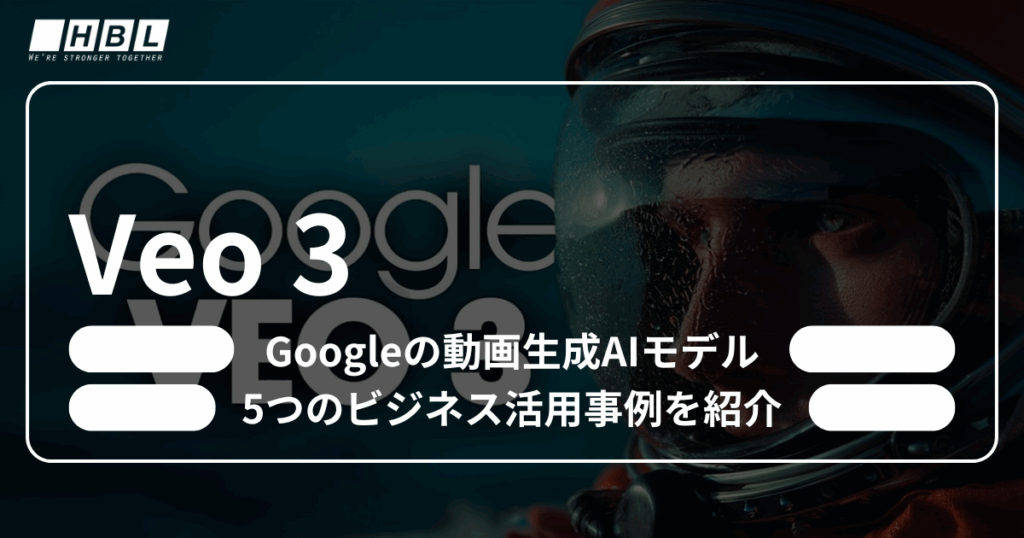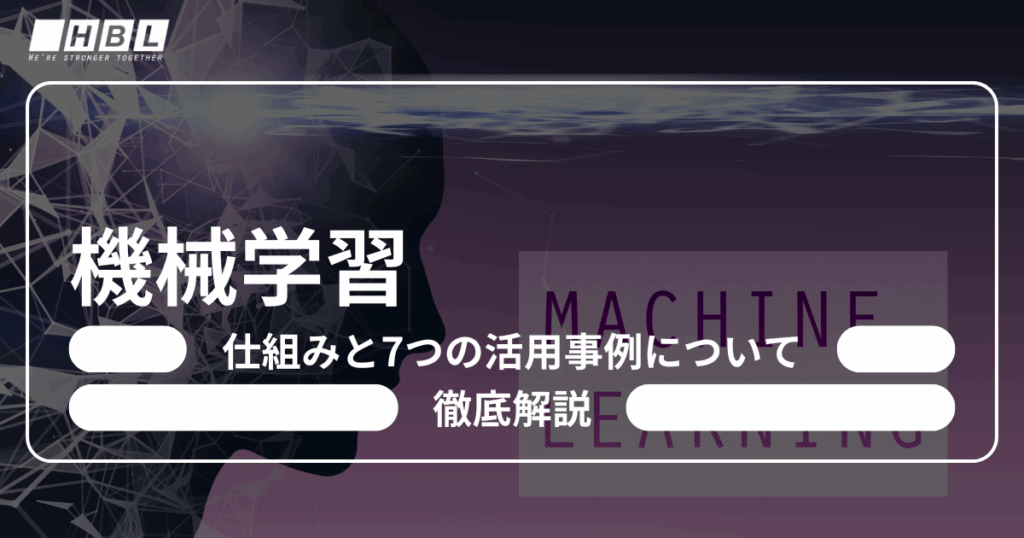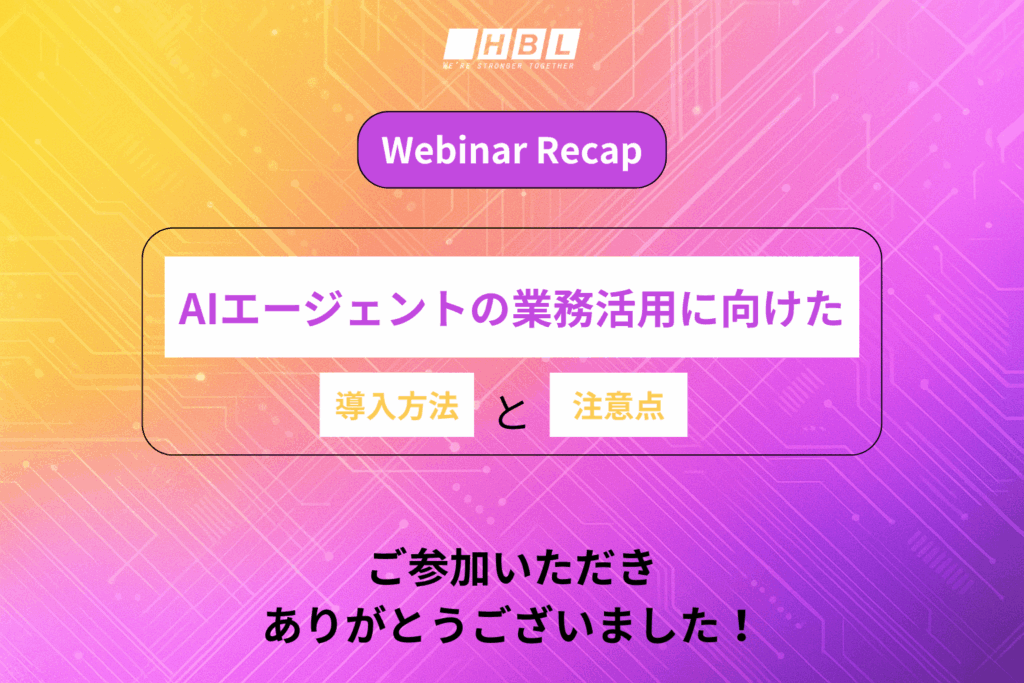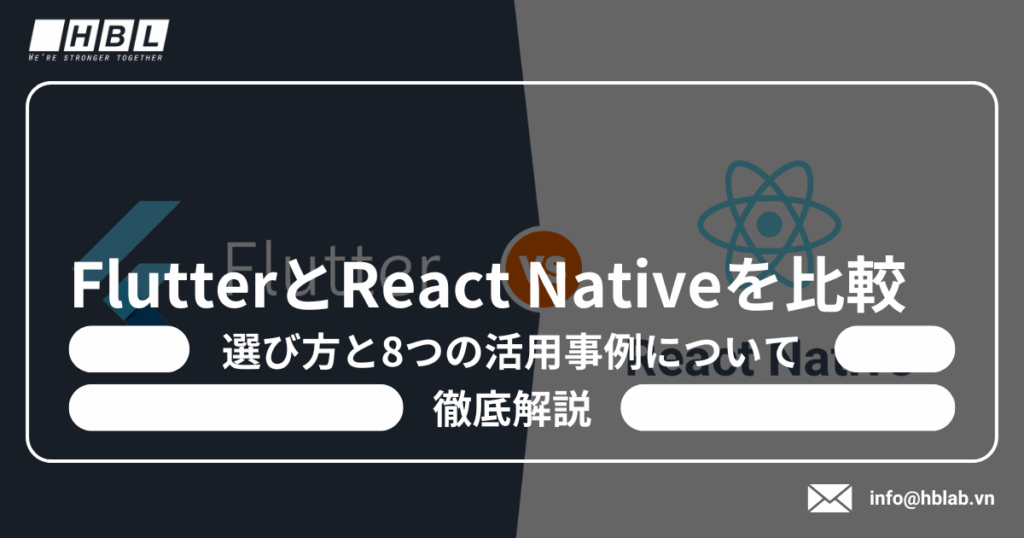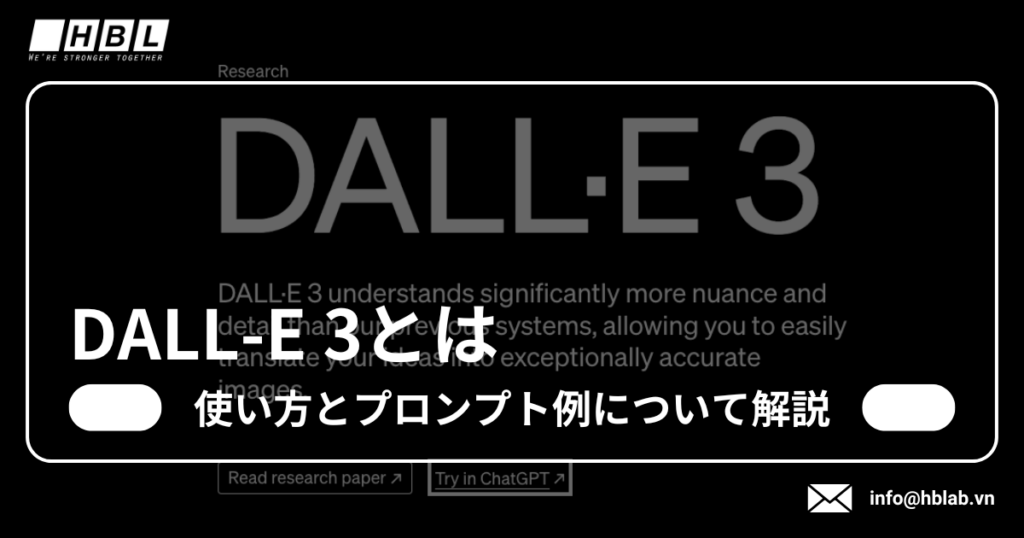エイチビーラボ、ガートナージャパン主催イベント「アプリケーション・イノベーション & ビジネス・ソリューション サミット」に出展
出展のお知らせ 2025年6月18日(水)〜19日(木)開催の「ガートナー アプリケーション・イノベーション&ビジネス・ソリューション サミット」に、弊社は出展企業として参加いたします。以下のようなソリューションをご紹介いたしますので、ぜひ弊社ブースにもお立ち寄りください。 ・爆速マイグレーションを実現する、AI×ローコード×グローバル体制 AIによるコード変換、ローコード開発手法、そしてベトナムを中心としたグローバル開発体制などを組み合わせることで、従来よりも圧倒的にスピーディーかつ高品質なシステムマイグレーションを実現します。要件定義から設計・開発・テストまでを一貫して対応し、コスト最適化と短納期を両立します。 ★ AIコード変換ツール「AIConverter」のデモ動画をブース内でご紹介します!★ ・AI人材1000人体制で、企業のAI活用をトータル支援 HBLABは、2030年までに「AI人材1000人体制」の構築を目指し、企業のAI導入・活用をトータルで支援しています。社内AIチームによる内製化支援、社員向けのカスタマイズ可能なAIトレーニング、ベトナムの大学との連携による専門人材の安定供給などを通じて、企業が持続的かつ自律的にAIを活用できる体制構築を力強くサポートします。 HBLABは、ツール・開発体制・人材育成を三位一体で推進し、単なるAIソリューション提供にとどまらず、企業が自らAIを活用し続けられる未来の基盤づくりに取り組んでいます。 出展概要 開催日:2025年6月18日(水)〜19日(木) 場所:ウェスティンホテル東京 […]
エイチビーラボ、ガートナージャパン主催イベント「アプリケーション・イノベーション & ビジネス・ソリューション サミット」に出展 続きを読む