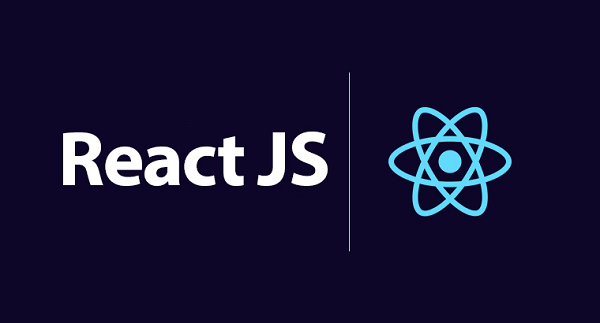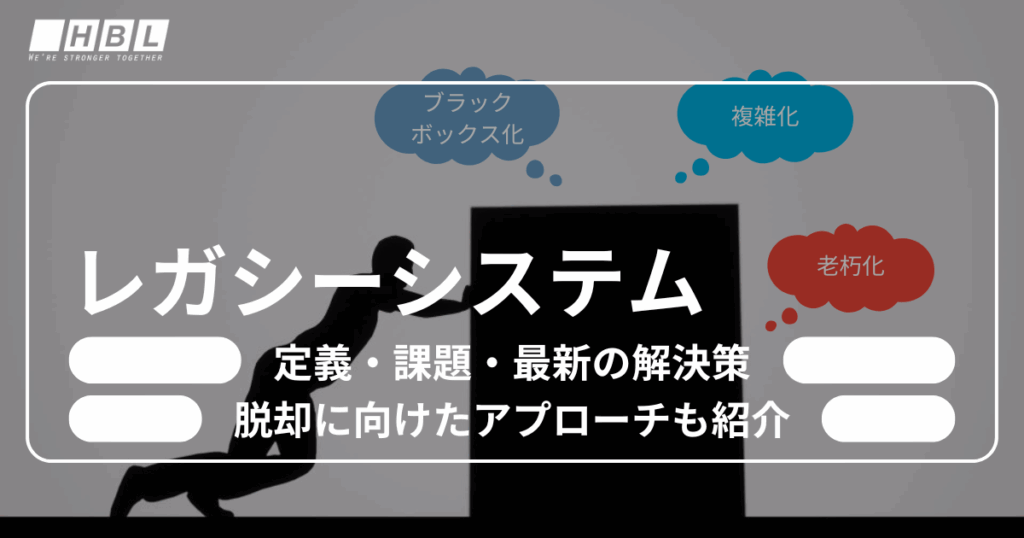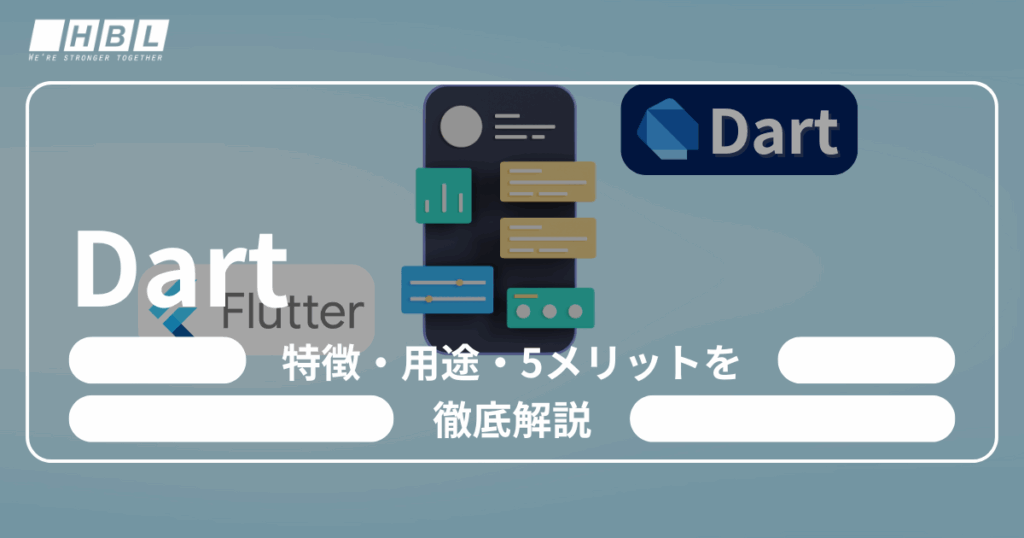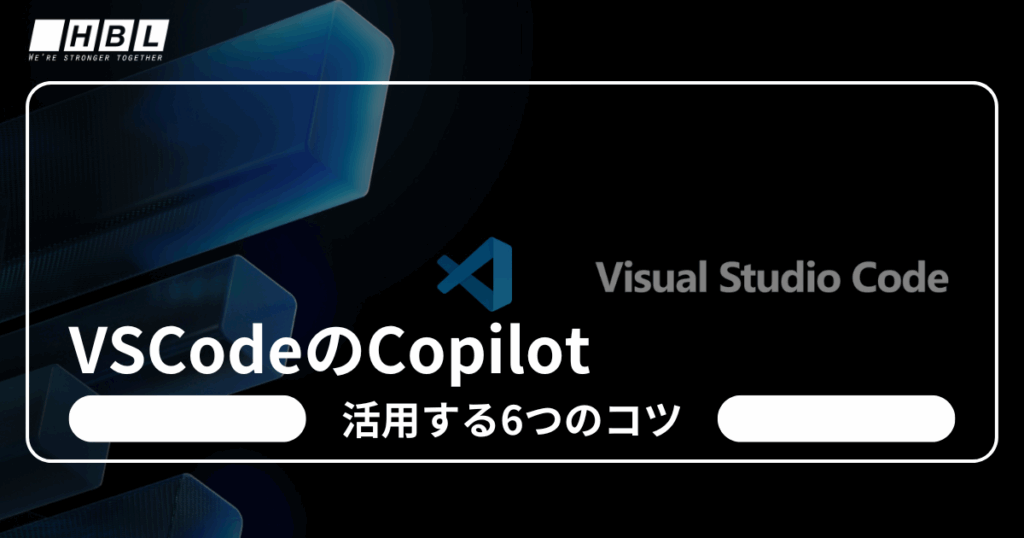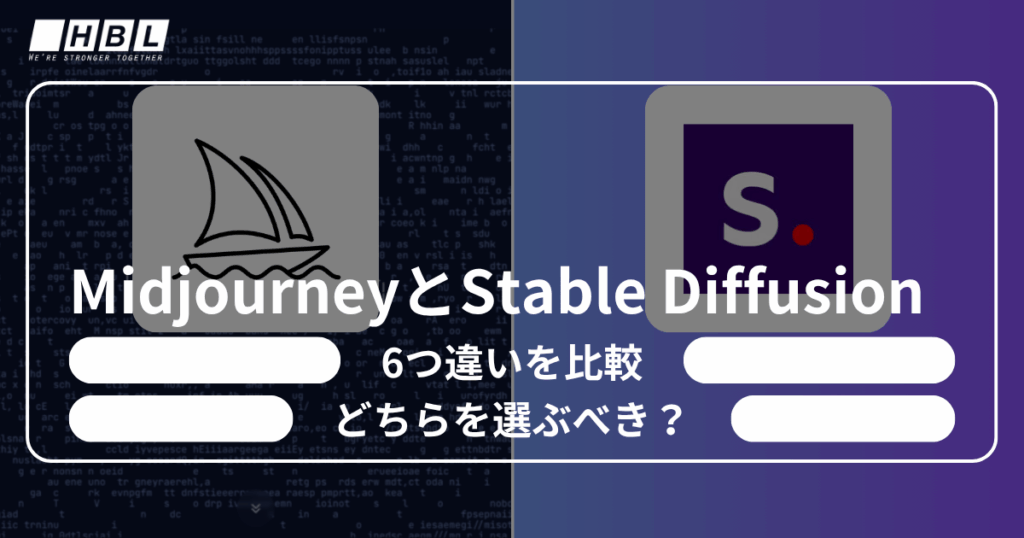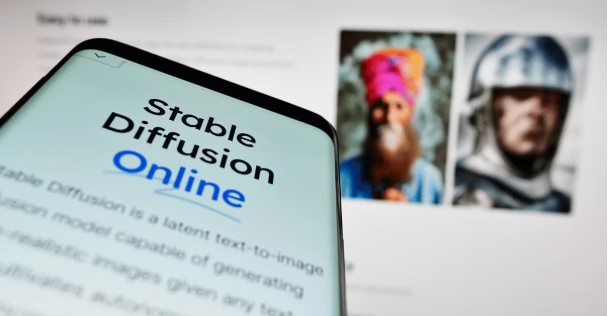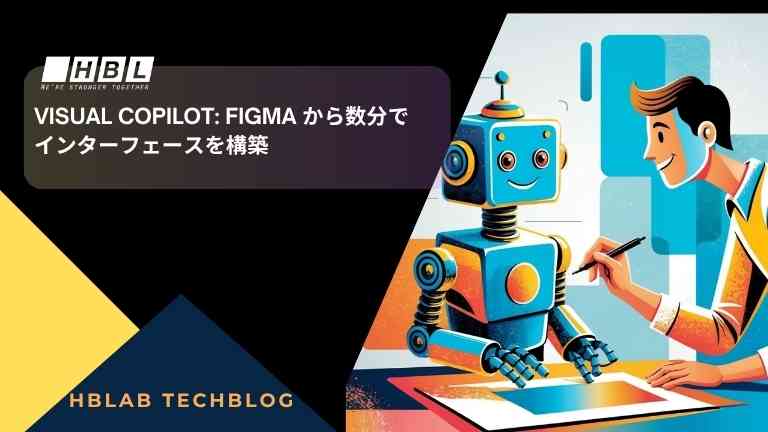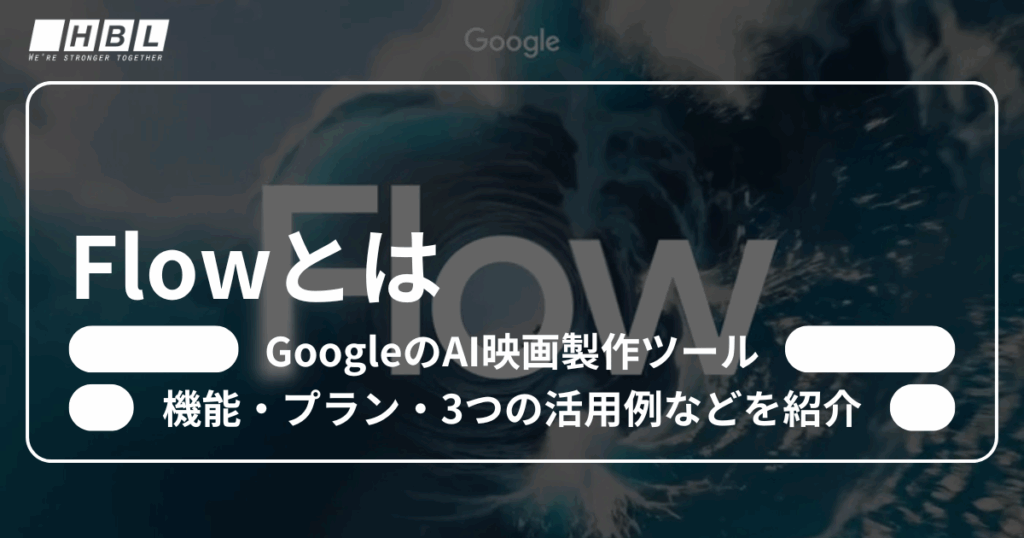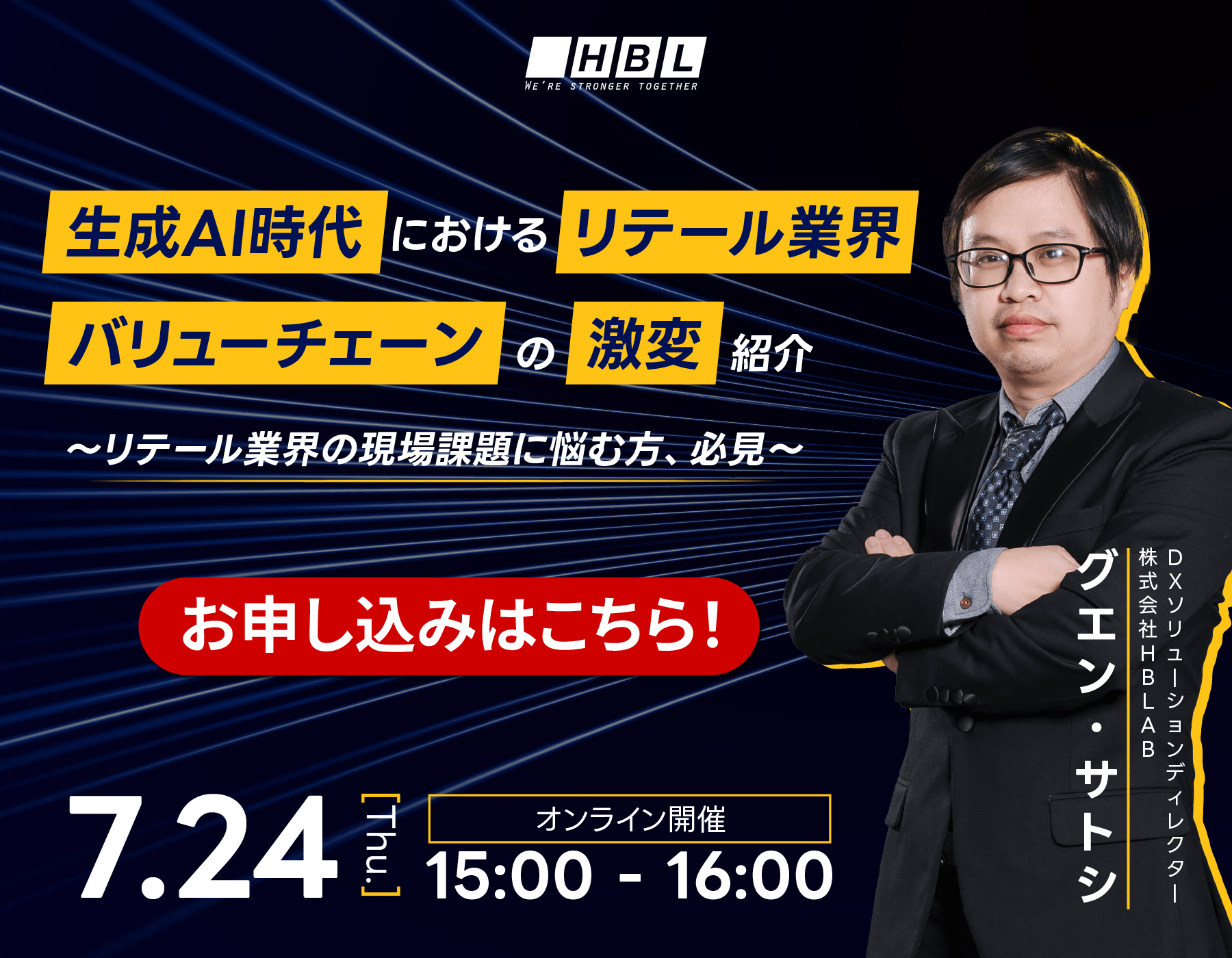JavaScriptとは?Web開発に欠かせない5つの特徴とReact Nativeとの関係
はじめに プログラミング言語の世界には、数多くの言語が存在し、それぞれが特有の特徴と用途を持っています。JavaScriptとReact Nativeは、現代のウェブおよびモバイルアプリケーション開発において不可欠な技術スタックの一部です。 その中で、JavaScriptは特に広く使用されている言語であり、異なる設計理念と実行環境に基づいています。開発用途は、Webサイト制作やアプリケーション開発などに使われているJavaScriptがトレンドとなっています。 本記事では、「JavaScriptとは何か?」という基本的な問いに答える形で、その特徴やできること、他の言語との違いなどをわかりやすく解説します。 JavaScriptとは? JavaScript(ジャバスクリプト)とは、Webページに動的な動きを加えるために広く使われているプログラミング言語です。HTMLやCSSと連携して、ユーザー操作に応じて画面を変化させるインタラクティブな機能を実現します。 1995年にNetscape社のBrendan Eichによって開発され、現在ではWeb開発に欠かせない技術の一つです。JavaScriptは、Webブラウザ内で動作する「クライアントサイドのスクリプト言語」として始まりましたが、近年ではNode.jsなどの登場により、サーバーサイド開発でも活用されるようになっています。 JavaScriptの歴史 JavaScriptは、1995年にNetscape社のBrendan Eich氏によって開発されました。もともとは「LiveScript」という名称でしたが、当時人気の高かったJavaにあやかって「JavaScript」に改名されました。 当初はブラウザ上で簡単な動きをつけるための軽量スクリプトとして利用されていましたが、その後、Web技術の進化とともに役割が拡大。1997年にはECMAScriptとして標準化され、2015年のES6では「クラス構文」「モジュール」「アロー関数」などが追加され、モダンな開発に対応する言語へと進化しました。 現在では、Webフロントエンドにとどまらず、Node.jsを通じたサーバーサイドや、モバイルアプリ開発(React […]
JavaScriptとは?Web開発に欠かせない5つの特徴とReact Nativeとの関係 続きを読む