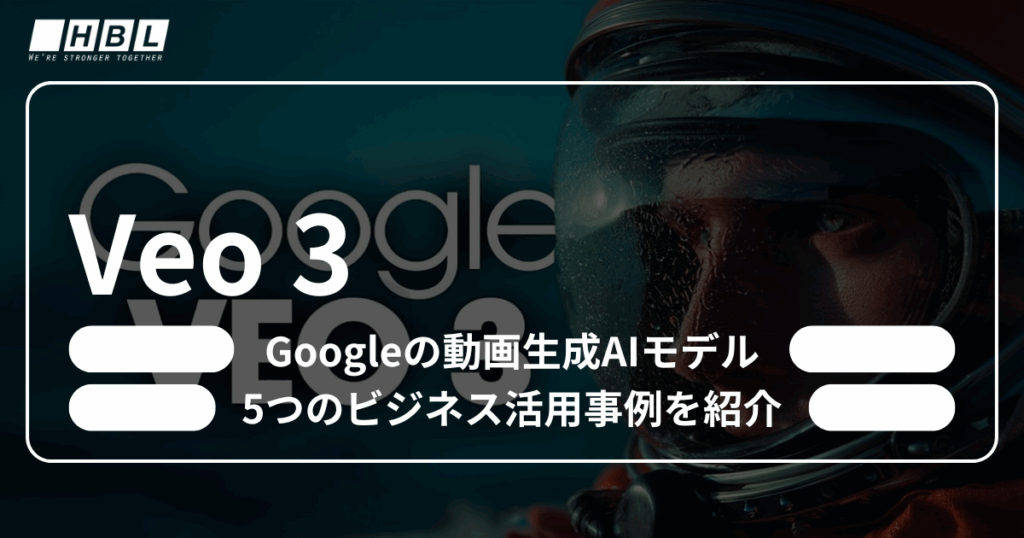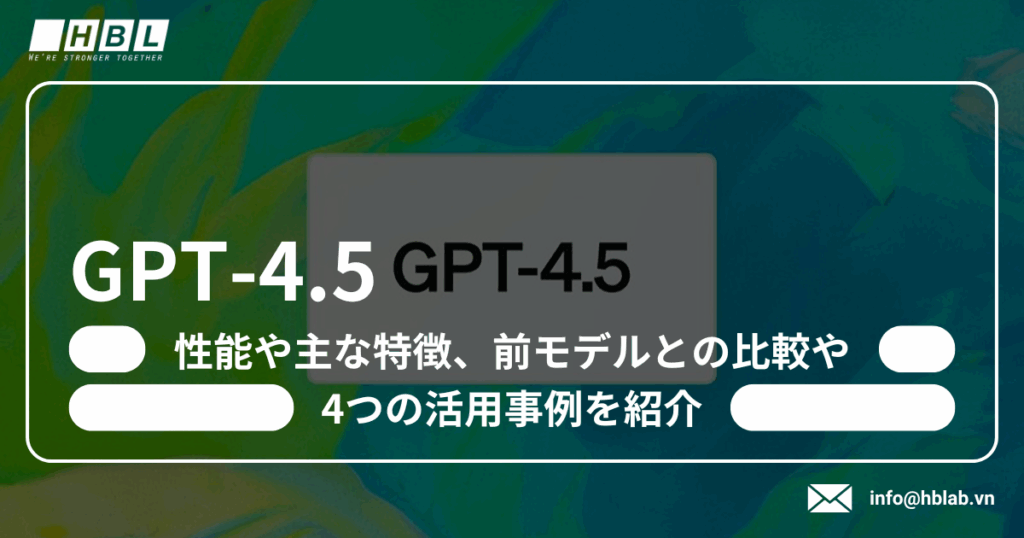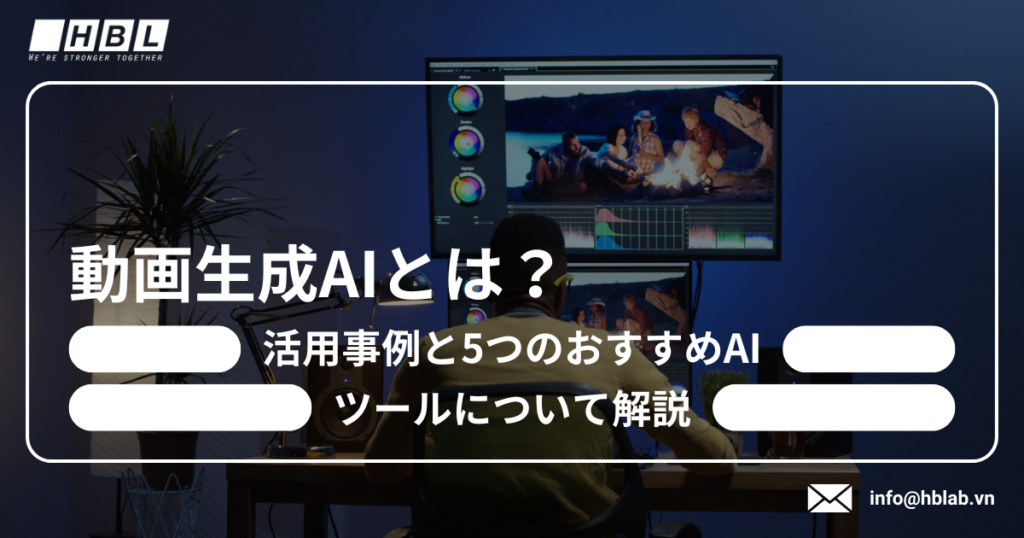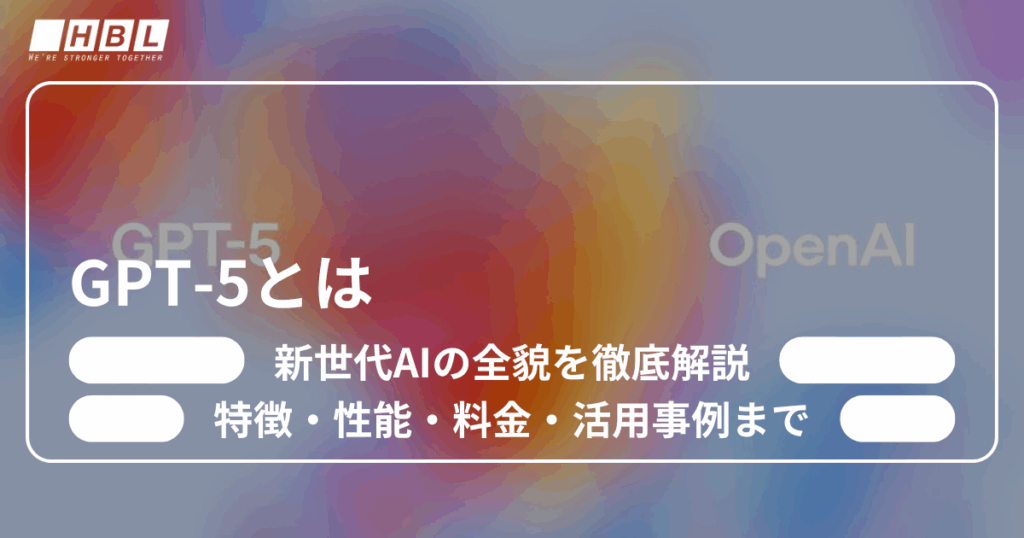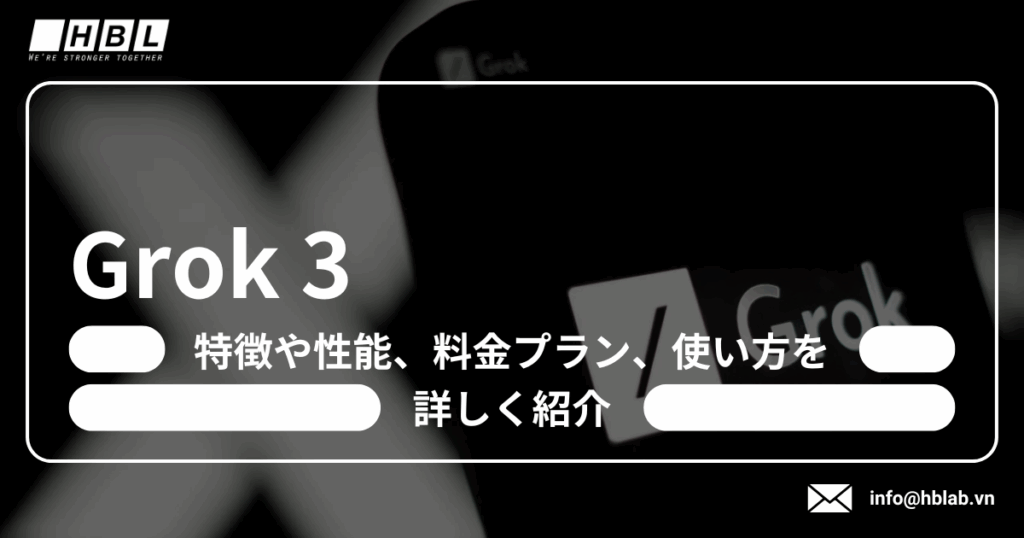Gemini 3とは何が変わった?前世代Gemini 2.5との違い・活用事例まで解説
はじめに 生成AIの進化が加速する中、Googleが発表した最新モデル「Gemini 3」は、前世代のGemini 2.5から大きな進化を遂げたモデルとして注目を集めています。 単なる性能向上にとどまらず、推論能力やマルチモーダル対応の強化、実務での使いやすさなど、実際の利用シーンを強く意識したアップデートが特徴です。 一方で、「Gemini 2.5と何が違うのか」「業務や開発で本当に使えるのか」といった疑問をもつ人も多いのではないでしょうか。 本記事では、Gemini 3で何が変わったのかを軸に、前世代2.5との具体的な違い、進化したポイント、さらに実際の活用事例までを整理して解説します。 これからGemini 3の導入や活用を検討している人にとって、判断材料となる情報をわかりやすくまとめています。 Gemini 3とは Gemini […]
Gemini 3とは何が変わった?前世代Gemini 2.5との違い・活用事例まで解説 続きを読む
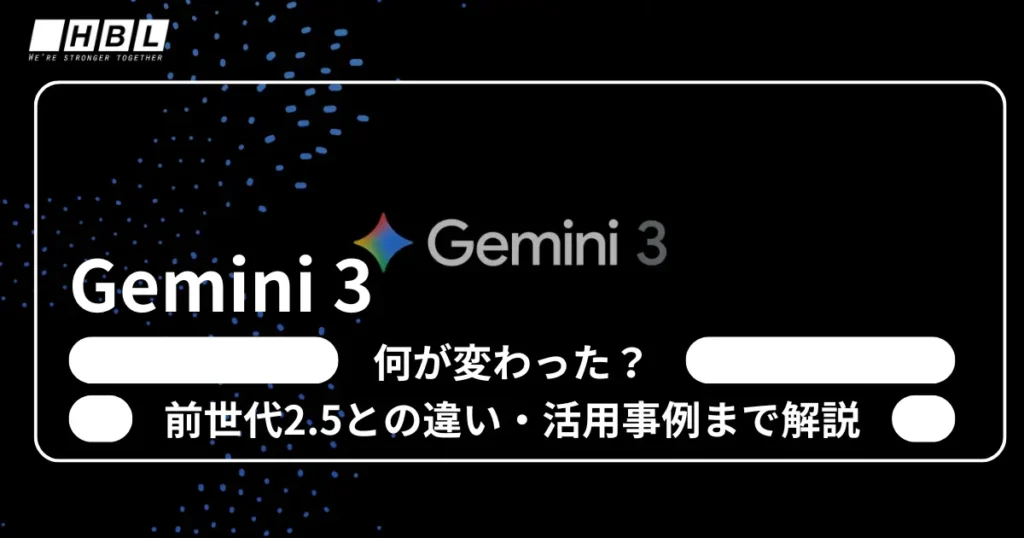
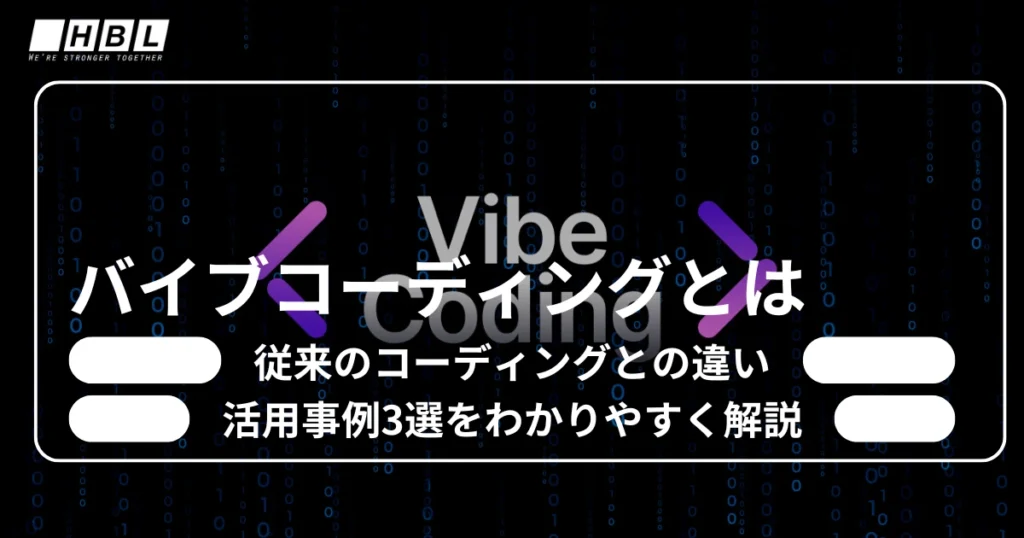
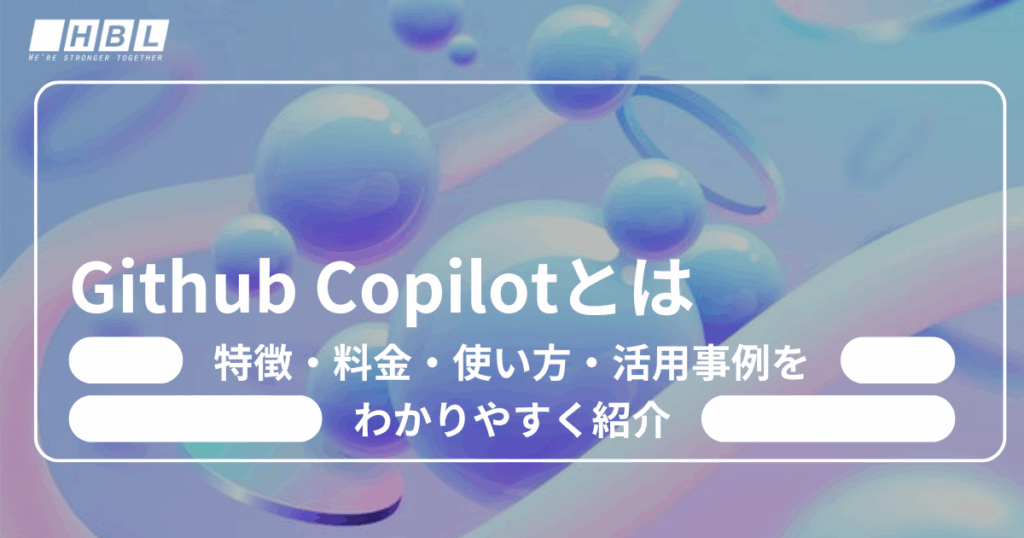
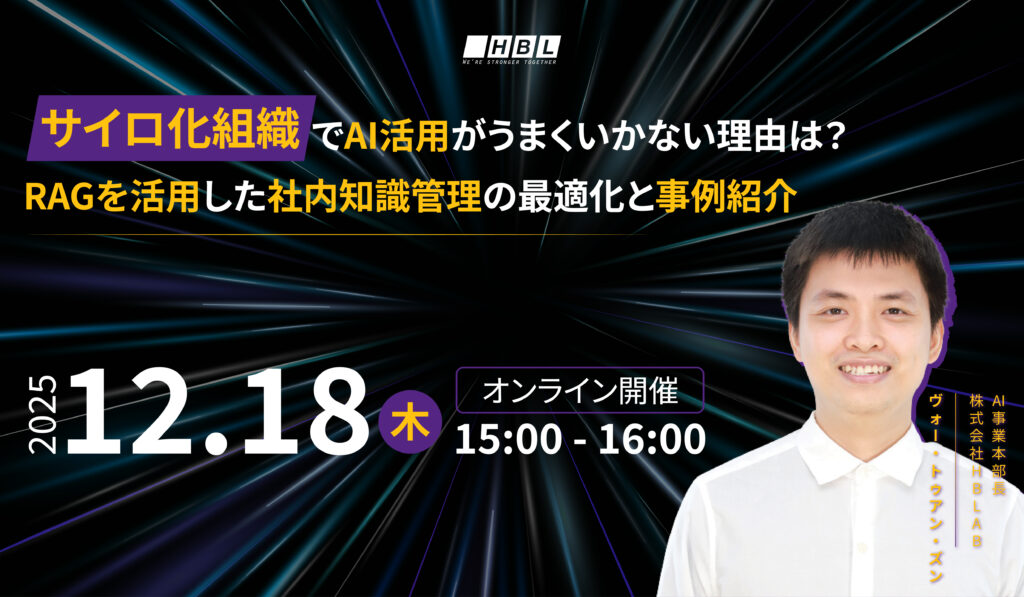
とは-1024x538.png)