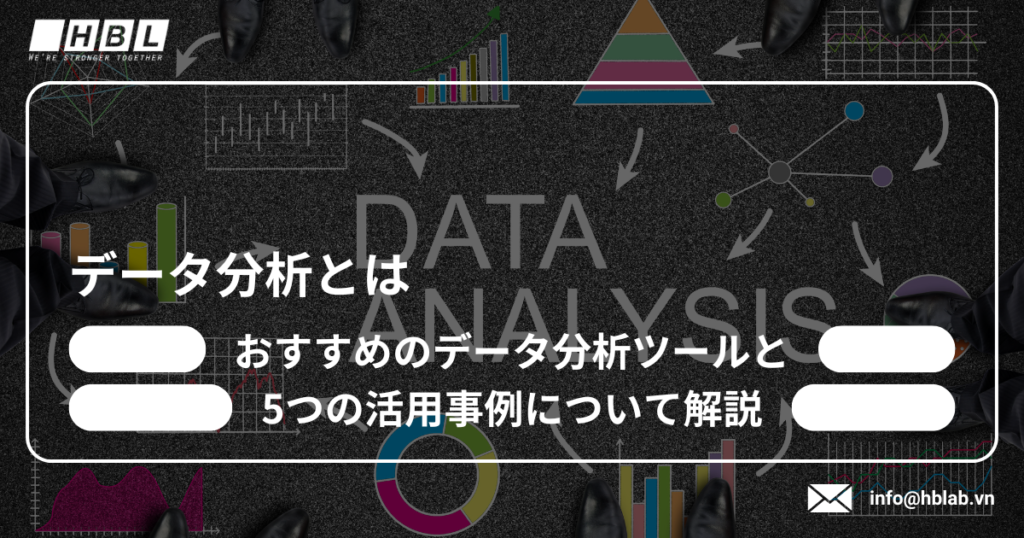2024年注目のWebアプリ開発フレームワーク5選について解説
はじめに Webアプリ開発におけるフレームワークとは、共通する処理部分のプログラムを自動的に作成してくれる枠組みです。Webアプリ開発フレームワークは、アプリケーション開発のプロセスをサポートし、エラーを減らした作業が実現できます。 近年では、システム開発にフレームワークを導入する企業が増えていて、開発速度の向上に対する需要が高まっています。しかし、フレームワークを選ぶ際は、開発者のスキルセットや定期的なアップデートに対応できるかどうかチェックすることが大切です。 自社でWebアプリケーション開発でフレームワークを使用したいがどのように選べばいいのか気になる方は多いはずです。本記事では、Webアプリ開発フレームワーク5選について詳しくご紹介していきます。 Webアプリ開発フレームワークとは? フレームワークとは、開発者がアプリケーションを効率的に構築するための「枠組み」を提供するためのツールです。フレームワークはWebアプリやWebサイトを作るのに、プログラミング言語をゼロからコーディングするより既存のテンプレートでコードを記述します。 フレームワークは本来、デスクトップアプリケーションやモバイルアプリケーションなどを開発するために使用することができます。アプリ開発において代表的なフレームワークでは、Python用のDjangoやPHP用のLaravel・Ryby on Railsなどが多く開発者の間で使用されています。 フレームワークはプログラミングの再利用可能なコードを提供することで、開発者の生産性を向上させることができるのが特徴です。従来はプログラミング言語を最初から書く必要がありましたが、フレームワークでは同じコードを毎回書き直す必要がないので大幅に時間を節約することができます。 これにより、フレームワークは基本的なコードや共通処理を再利用することで、開発時間を短縮し、コスト削減にもつながります。 フロントエンドフレームワーク フロントエンドフレームワークとは、WebアプリケーションやWebサイトのユーザーインターフェースを効率的に開発するためのフレームワークです。フロントエンドフレームワークでは、効率的な開発に特化していて、再利用可能なコードを作成することができます。 そもそもフロントエンド開発とは、ユーザーが直接見るUIの部分や操作する部分のシステムを開発することです。具体的には、HTMLとCSS・JavaScriptを使用して、視覚的に使いやすいインターフェースを作成します。 […]
2024年注目のWebアプリ開発フレームワーク5選について解説 続きを読む
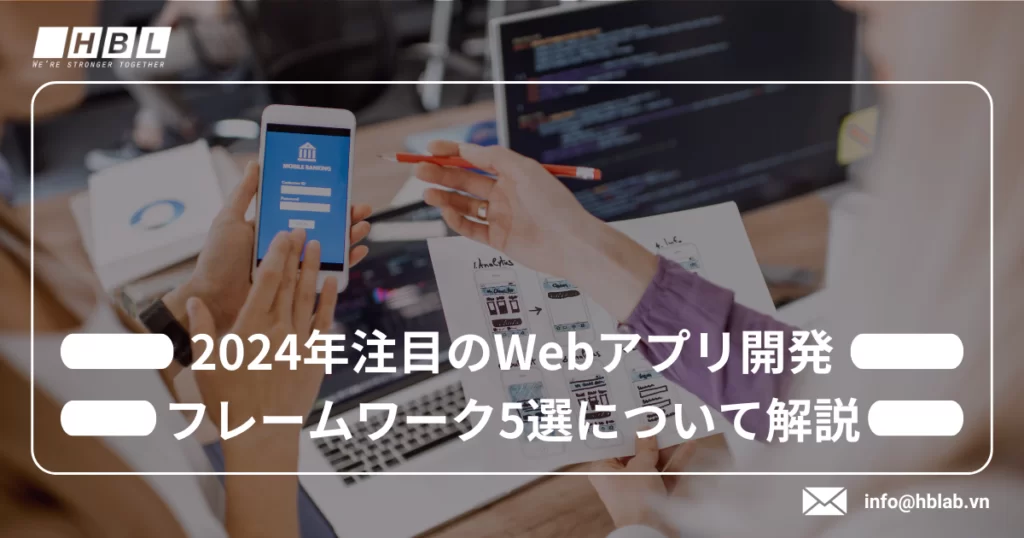


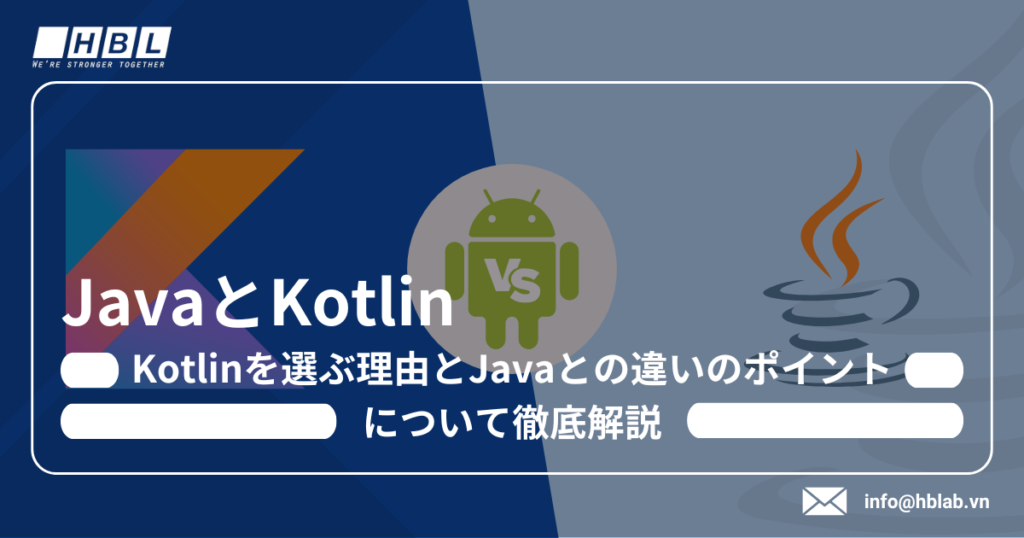
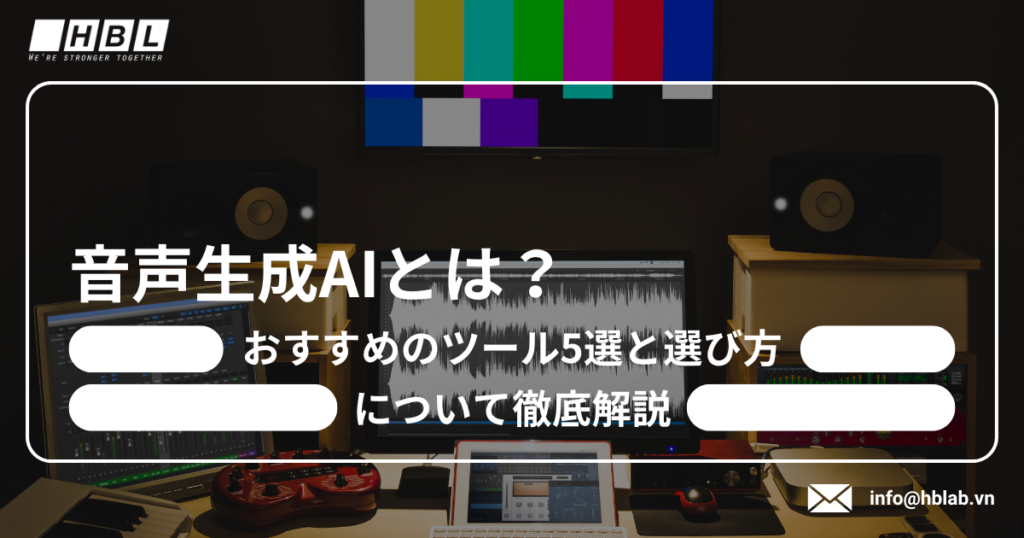

とは-1024x538.png)