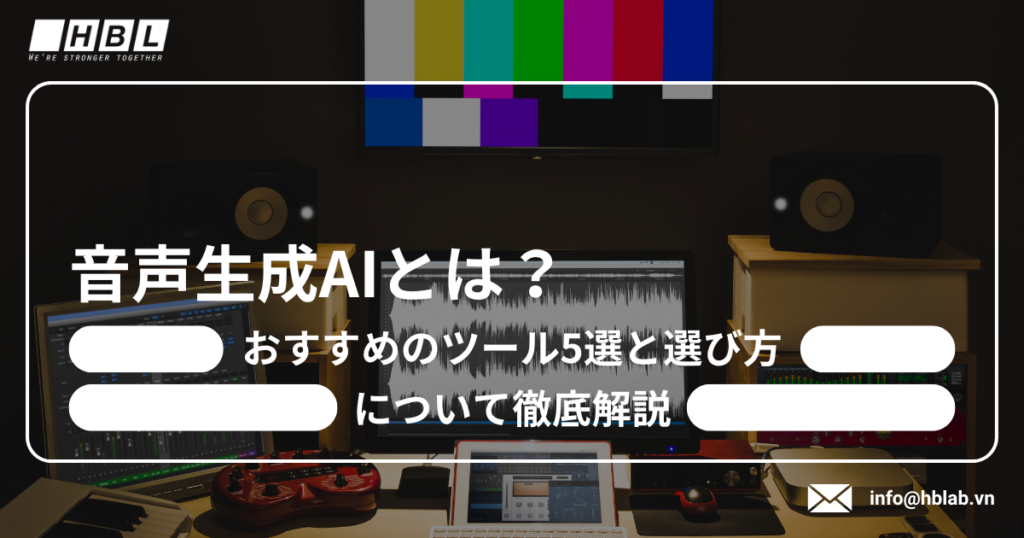プログラミングにおけるソフトウェアテスト種類6選を徹底解説
はじめに ソフトウェア開発において、テストは、アプリケーションの品質と安定性を確保するために欠かせないプロセスです。プログラミングにおけるテストは、開発者がバグを発見し、ソースコードを最適化し、ソフトウェアが期待通りに動作することを保証する役割を果たします。 ソフトウェアテストとは? ソフトウェアテスト(software testing)とは、ソフトウェアが正しく動作し、要件を満たし、エラーがないことを検証および確認するプロセスです。ソフトウェアテストの主な目的は、製品がエンドユーザーにリリースされる前にバグを発見し、ソフトウェアの品質と信頼性を確保することです。 プログラミングにおけるソフトウェアテスト種類 ソフトウェア開発の目的や段階に応じて、さまざまなソフトウェアテストの種類が存在します。以下に、基本的で一般的なソフトウェアテストの種類ノ6選を紹介します。 1. Unit Testing(ユニットテスト / 単体テスト) ユニットテストは、関数やメソッドなど、ソースコードの最小単位を対象としたソフトウェアテストです。各コード単位が正しく動作するかを確認します。JavaではJUnit、.NETではNUnit、Pythonではpytestなどのツールが一般的です。ユニットテストは、開発者がコードを書く過程で実施されます。 2. […]
プログラミングにおけるソフトウェアテスト種類6選を徹底解説 続きを読む


とは-1024x538.png)
とは-1024x538.png)

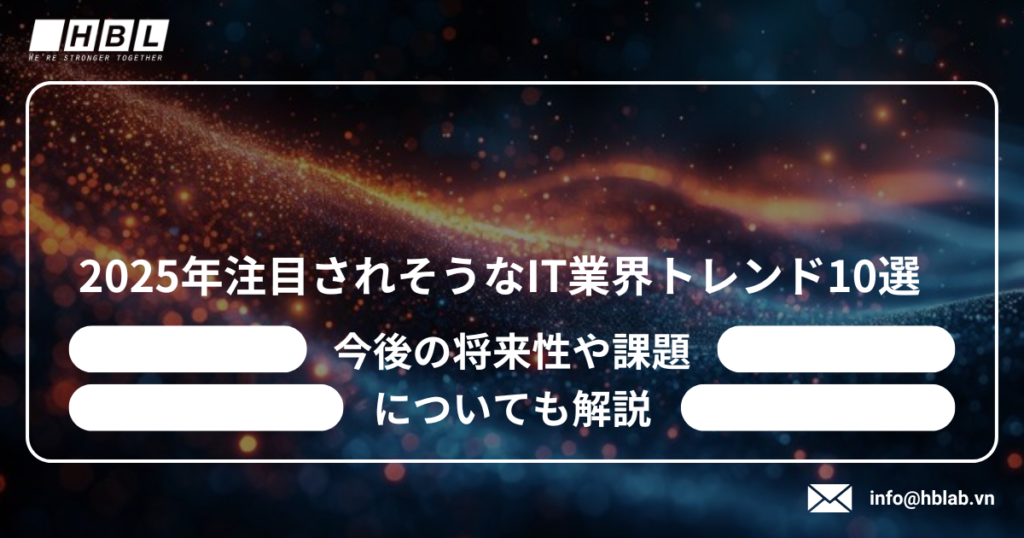
とは-1024x538.png)
とは-1024x538.png)