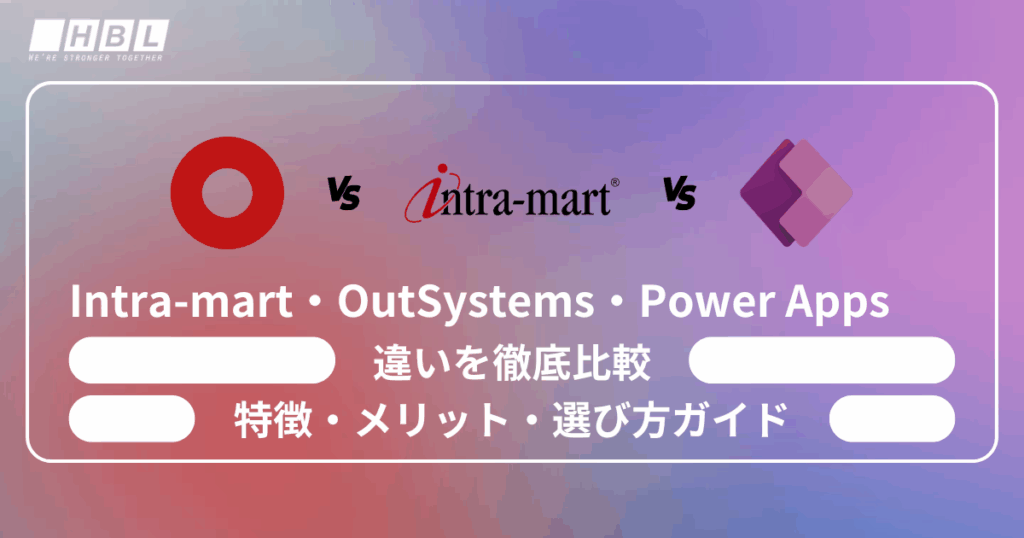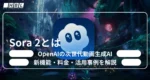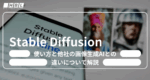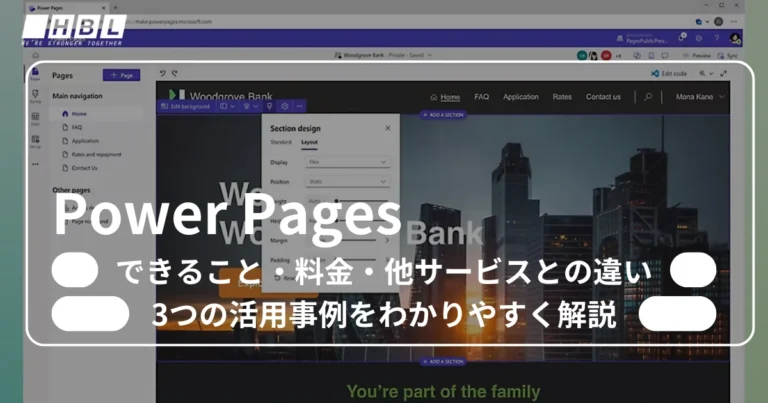はじめに
企業のデジタル化が急速に進む中、システム開発にかかる時間やコストを削減しつつ、現場ニーズに即応できる仕組みが求められています。その解決策として注目されているのがローコード開発ツールです。プログラミングスキルを持たない社員でもアプリケーションを構築できるため、IT部門の負荷軽減と業務効率化の両立が可能となります。
一方で、ツールごとに特徴や導入難易度、運用コストには大きな差があり、経営判断を誤ると「思ったほど効率化できない」「全社展開が進まない」といった課題に直面するケースも少なくありません。本記事では、国内外で利用が進む Intra-mart・OutSystems・Power Appsを比較し、それぞれの強みと注意点を整理します。経営者やマネージャーが自社に最適な選択を行うための指針としてご活用ください。
intra-mart(イントラマート)とは
とは.png)
intra-mart(イントラマート)は、株式会社NTTデータ イントラマートが提供する日本発のローコード開発・業務基盤プラットフォームです。特に国内の大手企業や自治体で導入実績が豊富で、ワークフロー、ポータル、文書管理、システム連携といった幅広い機能を標準搭載している点が大きな特徴です。
これにより、従来バラバラに管理されていた業務システムやデータを統合し、業務全体の効率化を支援します。 また、イントラマートは日本企業の商習慣や業務プロセスに即した設計が強みで、ERPや会計システムとの親和性も高く、業種ごとに柔軟にカスタマイズが可能です。さらに、オンプレミス・クラウドの両方に対応し、企業の規模やIT環境に合わせて最適な形で導入できる点も評価されています。
加えて、開発者向けの豊富なテンプレートや拡張ライブラリが用意されており、スピーディーなシステム開発が可能です。 近年はDX推進やテレワーク環境の整備といったニーズにも対応しており、業務のデジタル化と全社的な情報共有基盤の両立を支援する代表的な国内ローコードツールといえるでしょう。
OutSystemsとは
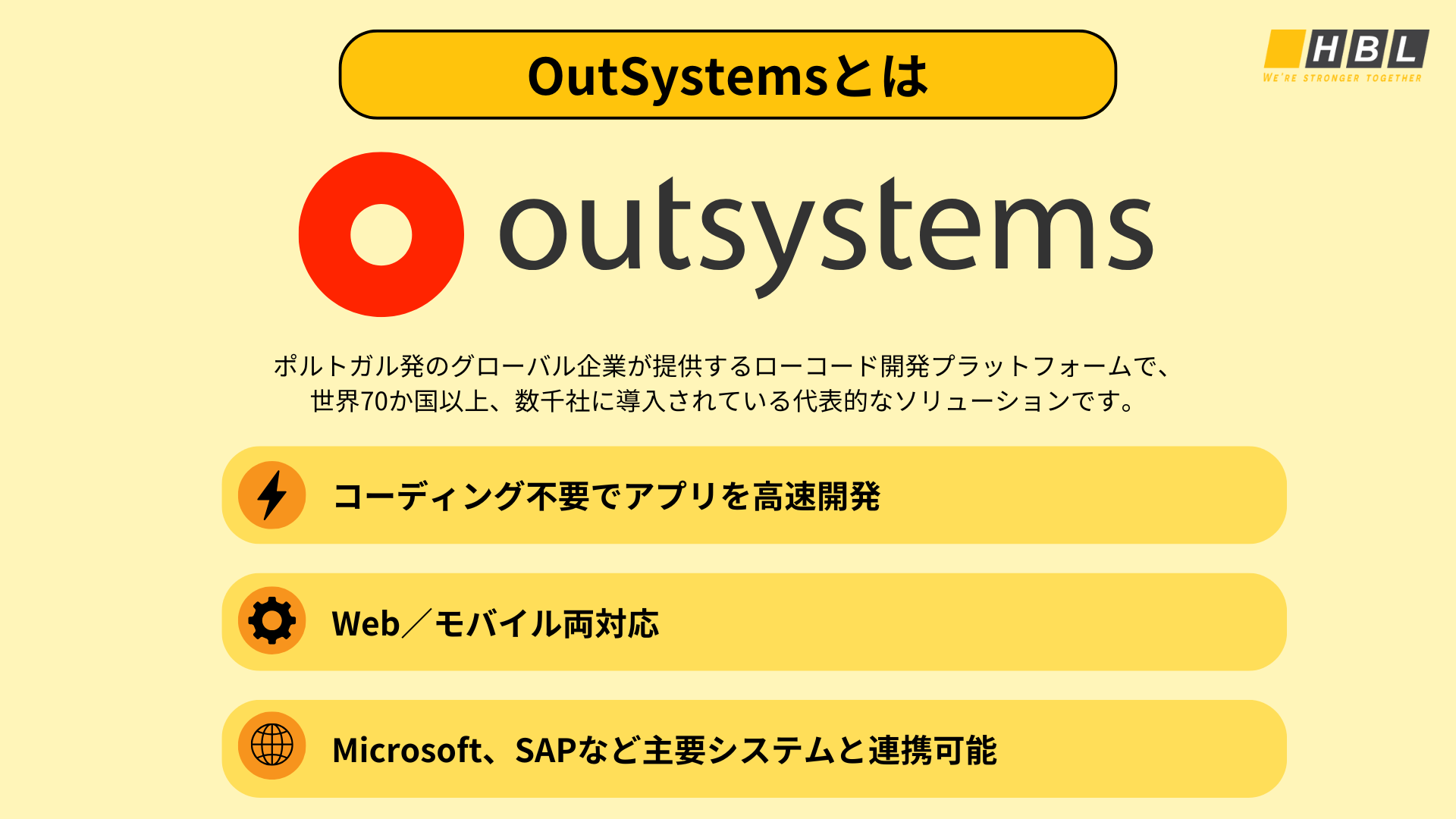
OutSystems(アウトシステムズ)は、ポルトガル発のグローバル企業が提供するローコード開発プラットフォームで、世界70か国以上、数千社に導入されている代表的なソリューションです。
エンタープライズ規模のシステム開発を得意とし、大規模かつ複雑な業務プロセスや顧客向けサービスを迅速にアプリ化できる点が最大の強みです。直感的なドラッグ&ドロップ操作でUIを構築できるだけでなく、既存のデータベースや外部システムとの連携機能が非常に強力で、レガシーシステムとの共存や段階的なモダナイゼーションにも適しています。また、クラウド、オンプレミス、ハイブリッドと多様な環境に対応しており、グローバル展開を目指す企業にとって柔軟性の高い選択肢となります。
さらに、OutSystemsはアジャイル開発やDevOpsを強力に支援しており、自動テストやCI/CDパイプラインとの連携機能を標準で備えているため、短期間でのリリースと継続的な改善が可能です。大規模ユーザー数や高負荷に対応するスケーラビリティも高く、金融や製造、公共機関などの業界で多く採用されています。総じて、OutSystemsは「スピード」「拡張性」「安定性」を兼ね備えたグローバル標準のローコードプラットフォームといえるでしょう。
Power Appsとは

Power Apps(パワーアップス)は、Microsoftが提供する「Microsoft Power Platform」の一部として展開されるローコード開発ツールで、Office 365やDynamics 365など既存のMicrosoft製品との高い親和性を持つ点が大きな特徴です。
直感的な操作でアプリを作成でき、業務部門のユーザーでも複雑なコーディングなしに独自のアプリケーションを構築できます。 特にExcelやSharePoint、Teamsとの連携が強力で、既存の業務データを活用したシンプルなアプリを短期間で導入できるため、現場の課題解決や業務改善に直結します。また、Power Automateとの組み合わせにより、ワークフローの自動化やAI機能の活用も可能となり、バックオフィスから営業活動まで幅広い領域で導入効果を発揮します。
さらに、Microsoft Azureとの連携を通じて、外部サービスやAPIとの統合も容易で、スモールスタートからエンタープライズ規模への拡張まで柔軟に対応できます。利用料金も比較的低コストで始められるため、中小企業から大企業まで幅広い導入が進んでいます。
Power Appsは、既存のMicrosoftエコシステムを最大限に活用し、業務効率化とDX推進を低コストで実現できるローコードプラットフォームとして、特にMicrosoft環境を日常的に活用する企業に最適な選択肢といえるでしょう。
intra-mart・OutSystems・Power Appsの特徴を比較
ローコード開発ツールは、開発効率化・業務効率化・DX推進の観点から多くの企業に導入が進んでいますが、ツールごとに強みや適した利用シーンが異なります。例えば、日本市場を中心に幅広い業務プロセスをカバーできるintra-mart、グローバル規模のシステム開発や大規模ユーザー数に対応できるOutSystems、Microsoftエコシステムとの親和性が高く導入しやすいPower Appsは代表的な選択肢です。
それぞれの特徴を理解することで、自社の課題や目的に合った最適なツールを見極められるようになります。
intra-martの特徴
intra-martは、日本企業の業務慣習に適合した設計を強みとするローコード開発基盤です。ワークフロー、ポータル、文書管理などの機能を標準搭載しており、ERPや会計システムとの統合が容易で、既存業務の延長線上でシステムを刷新できます。
また、クラウドとオンプレミスの両方に対応しているため、既存システムの構成を活かしつつ柔軟な導入が可能です。さらに、国内導入実績が豊富で、サポート体制も充実していることから、安心して利用できる点も評価されています。
日本市場向けに最適化されているため、製造業や金融業、公共機関など幅広い分野で導入が進んでいます。
OutSystemsの特徴
OutSystemsは、エンタープライズ規模の大規模開発を得意とするグローバル標準のローコードプラットフォームです。直感的なUI設計に加えて、既存システムや外部サービスとの高度な統合機能を持ち、複雑な業務アプリや顧客向けアプリを短期間で開発できます。
また、クラウド、オンプレミス、ハイブリッドと多様な環境に対応し、海外拠点を含むグローバル展開にも柔軟です。さらに、自動テストやCI/CD連携といったDevOpsを支援する機能が標準搭載されているため、継続的な改善や運用の効率化も実現可能です。
特にスケーラビリティに優れ、数千ユーザー規模の利用にも耐えられるため、金融・製造・公共分野などで採用が進んでいます。
Power Appsの特徴
Power Appsは、MicrosoftのPower Platformに含まれるローコード開発ツールで、Office 365やTeams、SharePointといった既存のMicrosoft製品と強固に連携できる点が最大の特徴です。業務担当者でも簡単にアプリを構築できるため、現場主導での小規模改善や迅速な業務効率化に適しています。
また、Power Automateと組み合わせることでワークフロー自動化やAIの活用も可能となり、DX推進を加速させます。低コストで導入しやすく、中小企業から大企業まで幅広く利用されている点も魅力です。特にMicrosoft環境を日常的に活用している企業にとっては、既存システムを拡張する最も自然な選択肢といえるでしょう。
intra-mart・OutSystems・Power Appsの違いを徹底比較
ローコード開発ツールを選定する際には、「どのツールが自社に最適か」を明確に判断するために、複数の視点で比較検討することが重要です。intra-mart、OutSystems、Power Appsはいずれも有力な選択肢ですが、対象とする市場やユーザー層、導入形態、拡張性、コスト体系などに違いがあります。
特に、国内業務に強いintra-mart、グローバルに展開するOutSystems、Microsoft製品と親和性が高いPower Appsは、それぞれの得意領域を持っています。以下の比較表と詳細解説を参考に、自社の業務環境やDX戦略に合ったプラットフォームを見極めていきましょう。
| 比較ポイント | intra-mart | OutSystems | Power Apps |
| 対象ユーザー・市場 | 日本市場に強み。中堅~大企業での業務プロセス改善に最適 | グローバル企業向け。多拠点・多言語対応に優れる | Microsoft 365利用企業に適合。中小~大企業まで幅広く対応 |
| 開発スピード・UI設計 | テンプレートや部品を活用し業務に沿ったUIを効率的に構築 | ドラッグ&ドロップ中心で迅速な開発。UI/UX自由度も高い | 直感的に操作可能。TeamsやExcelなどの既存UIとの統合が容易 |
| 業務適合性・機能範囲 | ワークフロー、文書管理、ERP統合など国内業務に強い | 業務アプリから顧客向けアプリまで幅広く対応 | 簡易アプリや業務改善用途に強み。Office製品と密接連携 |
| 導入形態 | クラウド・オンプレ両対応。既存環境を活かした導入が可能 | クラウド、オンプレ、ハイブリッド対応 | クラウド前提。Azure基盤との連携が中心 |
| 拡張性・スケーラビリティ | ERPや基幹システムとの統合に強く国内実績多数 | 数千~数万ユーザー規模に対応可能 | 小規模導入に強み。大規模利用はAzureとの連携が前提 |
| 運用・保守性 | 国内ベンダーによる手厚いサポートが魅力 | CI/CDや自動テスト標準搭載でDevOpsに最適 | Microsoft製品との統合により運用負荷を軽減 |
| コスト・ライセンス体系 | 個別見積もり型。規模や用途によって変動 | ユーザー数・アプリ数に応じたライセンス。大規模向け価格帯 | 比較的低コスト。ユーザー単位課金で導入しやすい |
| エコシステム連携 | ERP、国産SaaSとの親和性が高い | 多種多様な外部APIと連携可能 | Microsoft 365、Teams、Azureと高い親和性 |
対象ユーザー・市場
intra-martは日本市場を中心に、中堅から大企業の業務プロセス改善に強みを持ちます。OutSystemsはグローバル展開を志向する大企業に向いており、多言語・多拠点対応が可能です。一方、Power Appsは中小規模から大企業まで幅広く導入可能で、特にMicrosoft 365を利用している組織に適しています。
開発スピード・UI設計
OutSystemsはドラッグ&ドロップでの直感的なUI設計と強力な開発支援機能により、最も迅速な開発が可能です。intra-martはテンプレートや部品を活用して効率的に開発でき、業務システムに即したUI構築が得意です。Power AppsはMicrosoft製品のデータを活かしたシンプルなアプリ開発に向いています。
業務適合性・機能範囲
intra-martはワークフロー、文書管理、ERP統合など、国内業務に直結した機能を幅広く提供します。OutSystemsは業務系から顧客向けアプリまで幅広く対応でき、大規模開発に強いです。Power Appsはシンプルな業務改善アプリに強みを持ち、TeamsやSharePointなど日常業務ツールと連携して活用できます。
導入形態(クラウド/オンプレミス)
intra-martはクラウドとオンプレミス両方に対応し、既存システム環境を活かした柔軟な導入が可能です。OutSystemsもクラウド、オンプレ、ハイブリッドに対応しており、グローバル企業の複雑なIT環境に適合します。Power Appsはクラウド利用が前提で、Microsoft Azure環境との連携を前提とした設計です。
拡張性・スケーラビリティ
OutSystemsは数千〜数万ユーザー規模の利用に耐えられるスケーラビリティを誇り、エンタープライズ級の利用に最適です。intra-martも大企業での導入実績があり、ERPや基幹システムと統合する拡張性を持ちます。Power Appsは小規模導入から始められますが、大規模展開にはAzureとの連携が前提となります。
運用・保守性
OutSystemsはCI/CDや自動テストを標準搭載し、DevOps運用に強みがあります。intra-martは日本国内のベンダーサポート体制が整っており、安心感が高いのが特徴です。Power AppsはMicrosoft製品との統合により運用負荷を軽減できますが、複雑なカスタマイズは専門知識が必要になる場合があります。
コスト・ライセンス体系
intra-martは個別見積もり型で、規模や用途によって価格が変動します。OutSystemsは利用ユーザー数やアプリ数に応じたライセンス体系で、エンタープライズ向けの価格帯です。Power Appsは比較的低コストで、ユーザー単位の課金モデルが中心であり、中小企業でも導入しやすい点が魅力です。
エコシステム連携
Power AppsはMicrosoft 365やAzureとの強力な連携が最大の特徴で、既存のMicrosoft環境を活かせます。intra-martはERPや会計システム、国産SaaSとの親和性が高く、日本市場での活用がスムーズです。OutSystemsは多種多様な外部APIやサービスと連携可能で、グローバルなシステム統合に適しています。
intra-mart・OutSystems・Power Appsはどちらを選ぶべきか?
ローコード開発ツールを導入する際、どのプラットフォームを選ぶべきかは、企業の規模やシステム環境、目的によって大きく異なります。国内企業の業務プロセス改善に特化した intra-mart、グローバルな展開や大規模システム開発を強みとする OutSystems、そしてMicrosoft製品との高い親和性を持ち手軽に導入できる Power Apps。いずれも優れたツールですが、自社のDX戦略やIT投資の方向性に合わせた選定が求められます。
以下では、それぞれのツールを「どんな企業・どんなケースに適しているか」という観点から整理し、最適な選び方を解説します。
intra-martを選ぶべきケース

intra-martは、日本市場の業務慣習にフィットした設計と、ワークフローや文書管理といった標準機能を豊富に備えているため、国内企業にとって安心感のある選択肢です。特に、既存のERPや会計システムと統合しつつ、段階的にDXを進めたい中堅~大企業に適しています。
また、オンプレ・クラウド双方に対応しているため、現行のシステム環境を維持しながら移行できる柔軟性も魅力です。業務効率化だけでなく、国内ベンダーによる手厚いサポートを求める企業にも最適です。
OutSystemsを選ぶべきケース
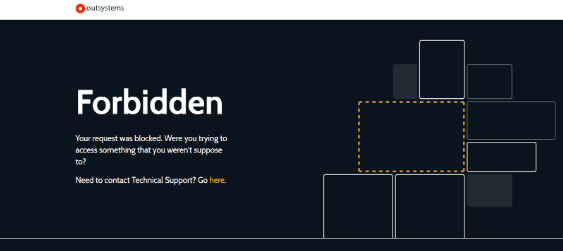
OutSystemsは、グローバル展開を視野に入れる大企業や、複雑な業務システムを短期間で開発したい企業に向いています。数千人規模のユーザーや大規模なデータ処理にも対応できるスケーラビリティを備えており、CI/CDや自動テスト機能により、運用フェーズでの効率化も可能です。
また、外部サービスや既存システムとの統合性が高いため、複雑なIT環境を持つグローバル企業に適しています。スピード感を持ってDXを推進し、競争力を強化したい経営層におすすめです。
Power Appsを選ぶべきケース

Power Appsは、Microsoft 365やTeams、SharePointなどを日常的に利用している企業に最適です。業務担当者自身が簡易アプリを作成できるため、現場主導で小規模な改善を進めたい組織に適しています。比較的低コストで導入できる点も魅力で、中小企業やスタートアップでも導入しやすいのが特徴です。
さらに、Power AutomateやAzureと連携することで、ワークフロー自動化やAI機能の活用も可能になります。手軽にDXを始めたい企業にとって、第一歩として選びやすいプラットフォームです。
まとめ
Intra-mart、OutSystems、Power Appsはいずれも優れたローコード開発ツールですが、対象市場や導入環境、強みはそれぞれ異なります。国内業務に強いIntra-mart、グローバル展開を支えるOutSystems、Microsoft環境と親和性の高いPower Apps。企業は自社のDX戦略やシステム環境に合わせて選定することが重要です。
HBLABでは、豊富なシステム開発経験と最新のローコード・AI技術を活かし、お客様の課題に最適なプラットフォーム選定から導入・運用まで一貫支援しています。