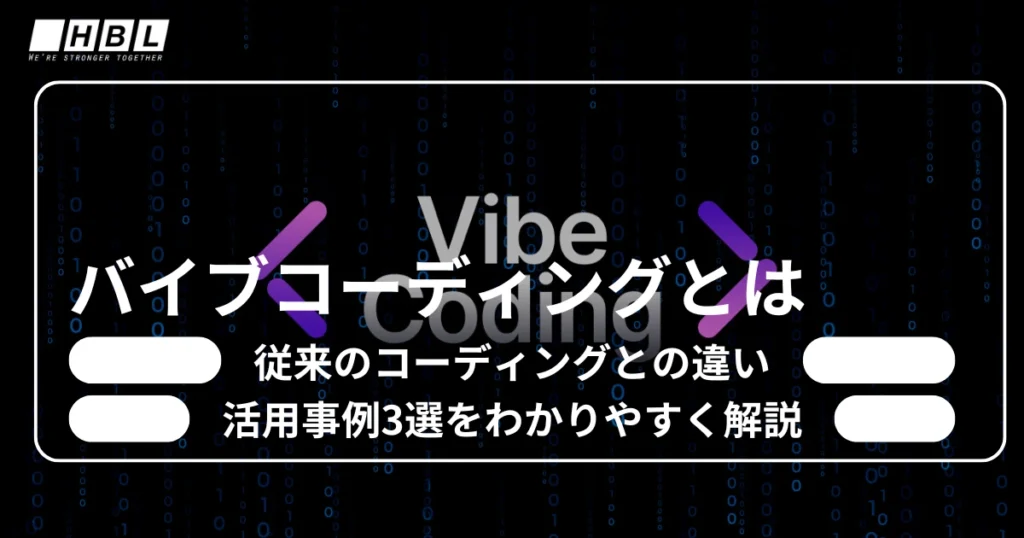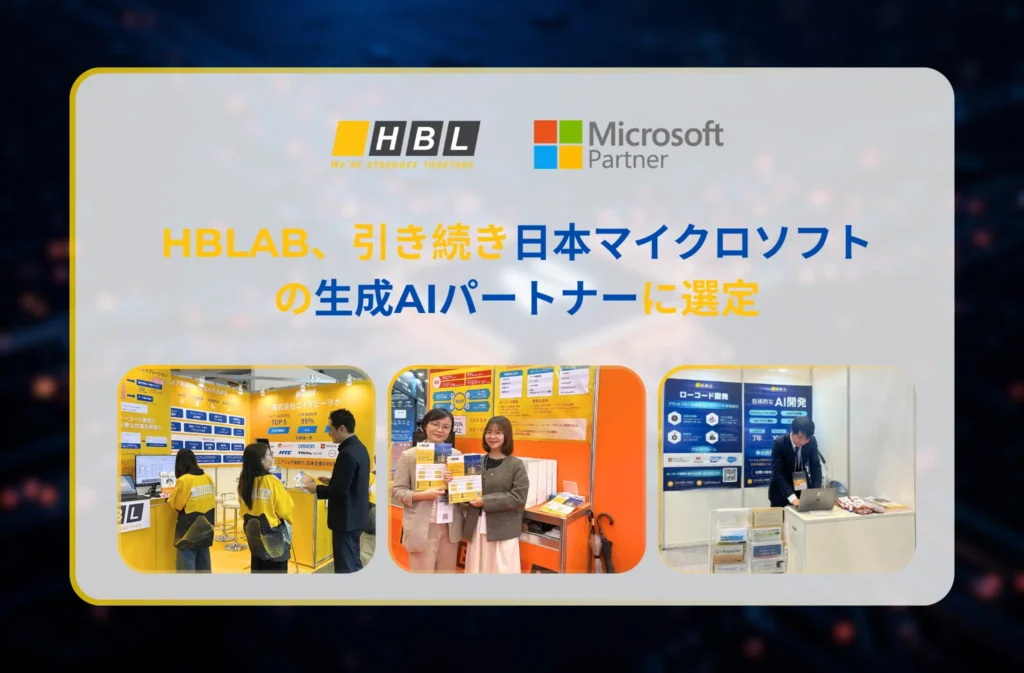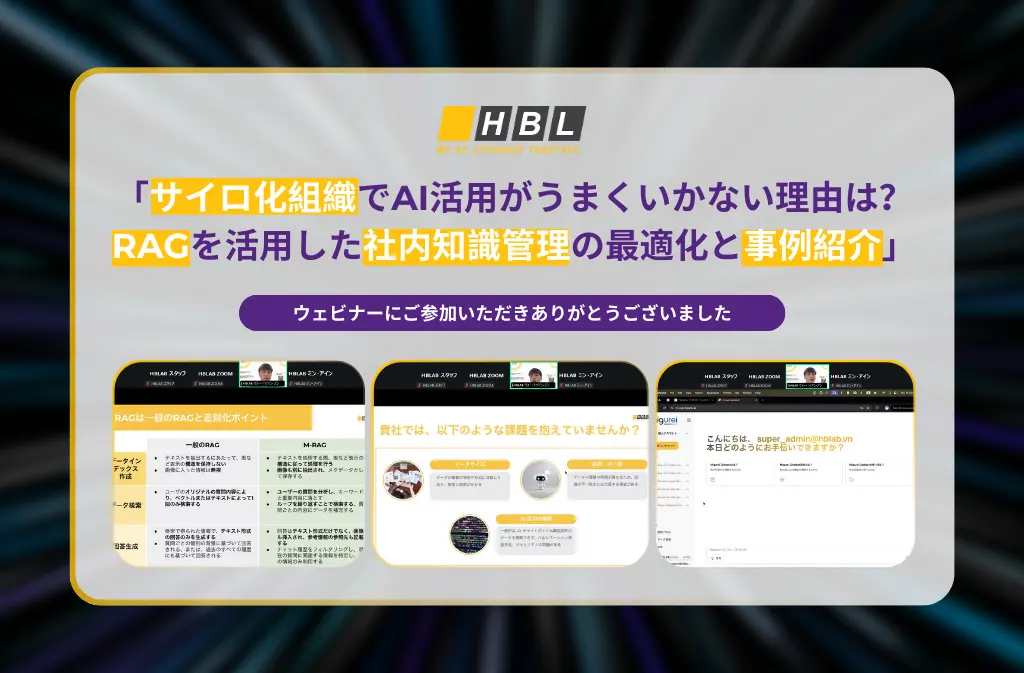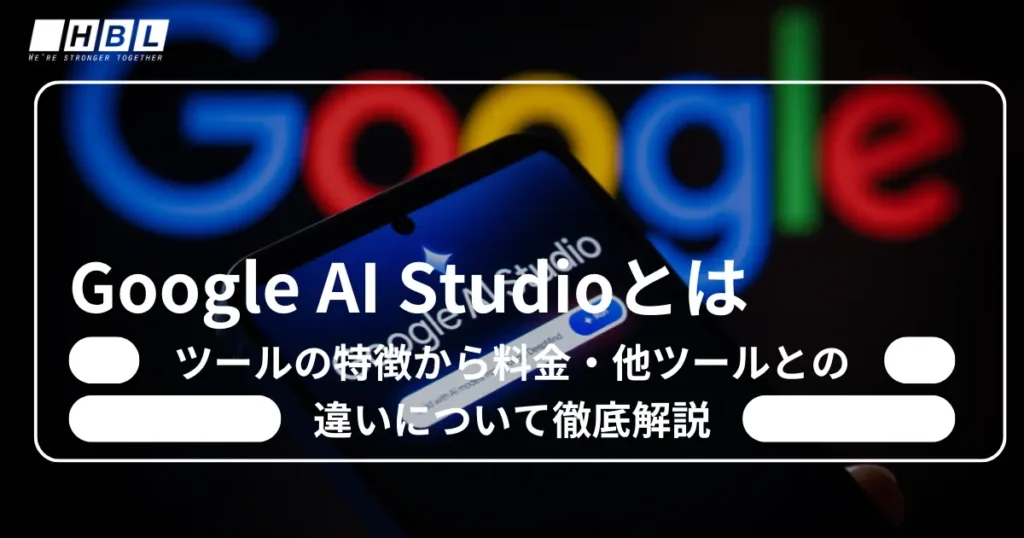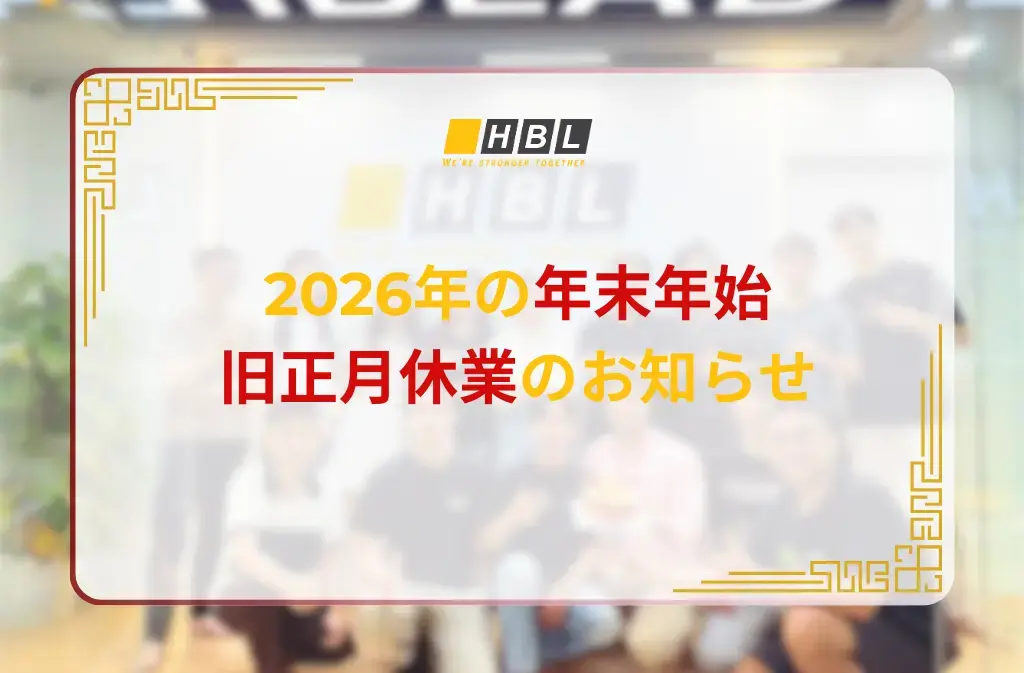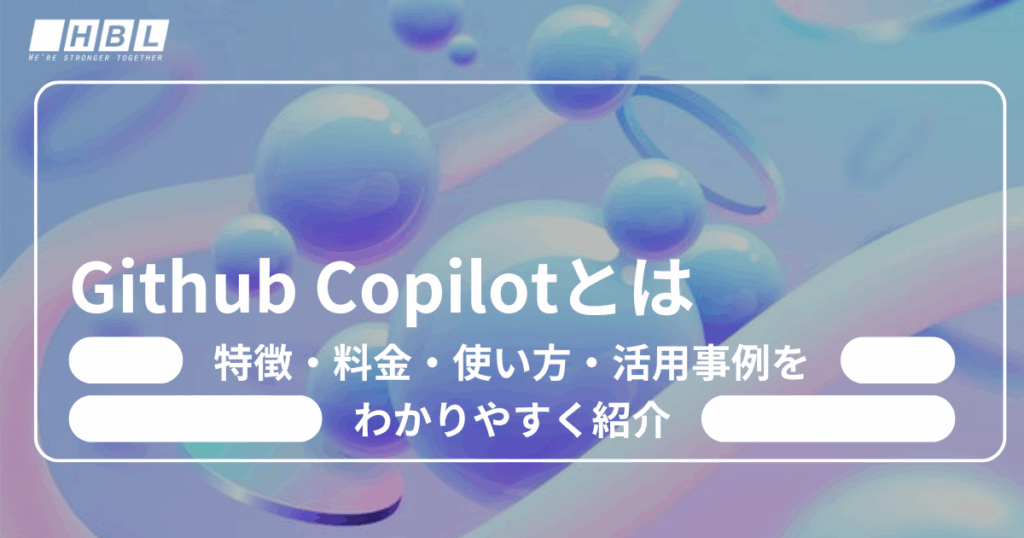バイブコーディングとは?意味・従来のコーディングとの違い・活用事例3選をわかりやすく解説
はじめに AIを活用した開発手法が進化する中で、「バイブコーディング」という言葉がエンジニアの間で注目を集めています。バイブコーディングとは、コードを一行ずつ厳密に設計・記述する従来のやり方とは異なり、AIに意図や方向性を伝えながら、試行錯誤を前提に開発を進めるスタイルを指します。 CursorやGitHub Copilot、Claude CodeといったAIツールの普及により、実装のスピードや柔軟性が大きく向上したことが、この考え方を後押ししています。一方で、「感覚的で危ういのではないか」「品質は担保できるのか」といった不安を感じる人も少なくありません。 本記事では、バイブコーディングの意味や基本的な考え方から、従来のコーディングとの違い、メリットや注意点を整理します。さらに、実際にバイブコーディングが活用されている事例も紹介し、どのような場面で有効なのかをわかりやすく解説します。AI時代の開発スタイルを考えるうえでの参考にしてください。 バイブコーディングとは バイブコーディングとは、AIの力を前提にしながら、人の意図や方向性を起点として開発を進める新しいコーディングスタイルです。従来のように最初から仕様や設計を細かく固めてコードを書くのではなく、「こうしたい」「この方向で動かしたい」といった感覚的なゴールをAIに伝え、試行錯誤しながら形にしていく点が特徴です。 CursorやGitHub Copilot、Claude CodeといったAIツールの進化により、コード生成や修正のハードルが大きく下がったことで、この考え方が現実的な選択肢として広がっています。ここでは、バイブコーディングの基本的な考え方や、従来の開発手法との違いを整理しながら解説します。 バイブコーディングは「意図」を起点にAIと進める開発スタイル バイブコーディングの最大の特徴は、コードそのものではなく「意図」から開発を始める点にあります。従来は、仕様書や設計書をもとに、どの関数をどう書くかを人が細かく決める必要がありました。 一方、バイブコーディングでは、「この機能を実現したい」「この挙動を改善したい」といった目的をAIに伝え、生成されたコードを見ながら調整を重ねます。AIが実装のたたき台を作り、人がそれを評価・修正する流れが前提です。 […]
バイブコーディングとは?意味・従来のコーディングとの違い・活用事例3選をわかりやすく解説 続きを読む