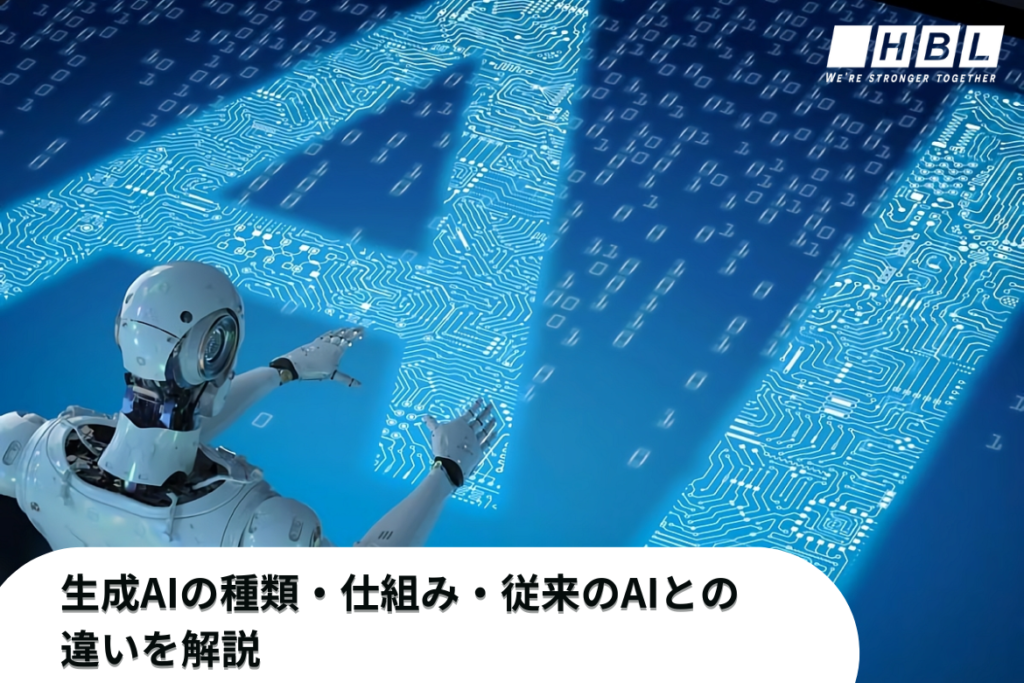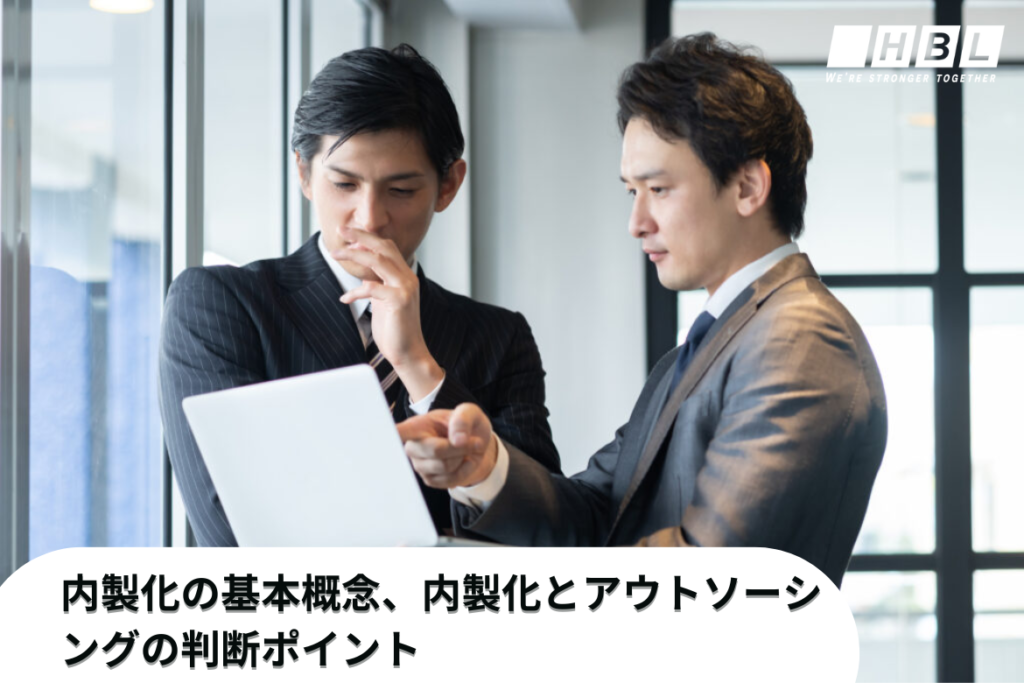生成AIの種類・仕組み・従来のAIとの違いを解説
初めに 生成AIは、近年急速に注目されている人工知能(AI)の分野の一つです。生成AIは、データから新しい情報やコンテンツを生成する能力を持ち、画像、音声、テキストなどの様々なメディアにおいて革新的な応用が期待されています。 本記事では、従来のAIとの大きな違いや、生成AIの種類、そしてそのモデルについて以下で詳しく解説します。 生成AIとは 生成AI(Generative AI)は、従来のAIとは異なるアプローチを用いて情報を生成する人工知能の一種です。従来のAIは、与えられたデータやパターンに基づいてタスクを実行することが主な目的でしたが、生成AIは新しいデータやコンテンツを創造することが可能です。 生成AIは文章や画像、音楽などを生成するのが一般的な利用法になります。 生成AIが注目される背景 生成AIが注目されるようになった理由はいくつかあります。 創造性と革新性 生成AIは新しいデータやコンテンツを創造する能力を持っており、これにより新しいアイデアやデザインの発展が可能になります。これは、芸術、デザイン、クリエイティブな産業だけでなく、科学やビジネスの分野でも革新的なアプローチを提供することができます。 自律性と柔軟性 生成AIは与えられた条件やデータに基づいて自律的に新しいコンテンツを生成することができます。これにより、人間の介入が少なくても創造的な成果を生み出すことができます。また、異なるデータや条件に対して柔軟に対応できるため、さまざまな場面で活用されます。 応用範囲の広さ […]
生成AIの種類・仕組み・従来のAIとの違いを解説 続きを読む