はじめに
企業のDX推進や業務効率化が加速する中で、近年注目されているのがローコード開発基盤「intra-mart」です。イントラマートはワークフロー管理を中心に、システム統合やアプリケーション開発を支援する国内発のプラットフォームで、20年以上の導入実績を誇ります。プログラミングの専門知識がなくても業務アプリを構築できる利便性や、既存システムとの柔軟な連携力が高く評価され、多くの企業が導入しています。また、Microsoft Power PlatformやOutSystems、kintoneといった他のローコード基盤との比較においても、導入規模や業務特化度で独自の強みを持っています。
本記事では、intra-martの基本概要から主な機能、導入メリット、他社製品との違い、さらに具体的な活用事例までをわかりやすく解説します。
intra-mart(イントラマート)とは
.png)
intra-martとは、NTTデータ イントラマート社が提供する企業向けのローコード開発プラットフォームであり、ワークフロー管理やシステム統合を強力に支援する基盤です。2000年の提供開始以来、国内外7,000社以上に導入されており、業種・規模を問わず幅広い企業の業務効率化やDX推進を支えてきました。
最大の特徴は、申請・承認といった日常業務を電子化・自動化するワークフロー機能に加え、ローコード開発によって短期間で業務アプリを構築できる点です。さらにERPや会計システム、人事・販売管理といった基幹システムとも柔軟に連携でき、企業内の情報やプロセスを統合的に管理できます。加えて、社内ポータル機能を通じた情報共有やタスク管理、RPAやAIとの連携による自動化強化にも対応しており、企業全体の生産性向上に寄与します。
イントラマートは「使いやすさ」と「拡張性」を兼ね備えた国産プラットフォームとして、DXを加速させる中核的な役割を果たしているのです。
intra-martの主な機能
intra-martは、単なるワークフローシステムにとどまらず、企業の業務基盤を包括的に支えるプラットフォームです。申請・承認といった日常業務の効率化はもちろん、ローコードによる業務アプリ開発、既存システムの統合、社内ポータルとしての情報共有まで、多彩な機能を一元的に提供します。さらに近年ではAIやRPAとの連携も強化され、DX推進の中核基盤として企業のデジタル化を加速させています。
ここでは、イントラマートの代表的な機能を5つに分けて紹介します。
ワークフロー管理機能
intra-martの中核機能であるワークフロー管理は、申請・承認といった業務プロセスを電子化し、スピーディかつ効率的に処理できる仕組みを提供します。紙ベースやメールベースのやり取りでは時間やコストがかかり、承認の滞留も発生しがちですが、イントラマートを導入することで申請内容の進捗をリアルタイムに可視化できます。
また、複雑な承認ルートや条件分岐にも対応可能で、企業独自の業務フローを柔軟に設定できる点も強みです。さらにモバイルからの承認やリマインド通知機能により、テレワークや外出中でもスムーズに業務を進行可能です。これにより、意思決定の迅速化と内部統制の強化を両立させ、全社的な業務効率化を実現します。
ローコード開発基盤
イントラマートはローコード開発基盤としても高く評価されています。プログラミングの専門知識がなくても、GUIベースでの画面設計やワークフロー構築が可能であり、現場部門が自ら必要な業務アプリを迅速に開発できます。これにより、従来は数週間から数か月かかっていたシステム開発が大幅に短縮され、業務要件の変化にも柔軟に対応可能です。
また、開発したアプリはイントラマートのプラットフォーム上で統合的に管理できるため、全社的な標準化と再利用性も高まります。さらに、従来型のスクラッチ開発と比較してコスト削減にも寄与するため、IT部門の負荷軽減やスピード重視のDX推進において大きな武器となります。
システム統合・基幹連携
イントラマートは、既存の基幹システムや外部アプリケーションと柔軟に連携できる点も大きな強みです。ERP、会計、人事、販売管理などの基幹業務システムと接続し、企業内に散在するデータを一元的に管理できます。これにより、システム間のデータ入力の二重化を防ぎ、業務効率とデータ精度を向上させることが可能です。
また、イントラマートは各種APIやWebサービスとも親和性が高いため、既存のIT環境を活かしながら段階的にDXを進められるのも特徴です。企業は全社の情報基盤を統合し、経営判断に必要なデータをタイムリーに活用できるため、競争力の強化にも直結します。
ポータル機能
イントラマートは、企業内の情報やコンテンツを集約し、従業員が必要な情報にスムーズにアクセスできる「社内ポータル」としても活用できます。タスク一覧やワークフローの進捗、掲示板やドキュメント共有、FAQなどを一元的に表示し、業務の出発点として機能します。さらに、利用者ごとにパーソナライズされた情報表示が可能で、部門や役職ごとに異なるニーズに対応できます。
ポータルを導入することで、従業員は複数のシステムにログインする手間がなくなり、利便性が大幅に向上します。また、情報が整理され可視化されることで、業務の属人化を防ぎ、組織全体のナレッジ活用を促進します。結果として、イントラマートは「情報のハブ」として従業員の生産性向上に大きく寄与します。
AI・RPA連携
近年のDX推進に欠かせないのがAIやRPAとの連携機能です。イントラマートは外部のRPAツールやAIエンジンとスムーズに接続でき、業務の自動化を一層加速させます。例えば、経費精算の明細入力をAIで自動認識し、RPAがシステムに登録するといった一連の流れを無人化することが可能です。
また、自然言語処理を活用して問い合わせを自動応答したり、データ分析をAIが行い、意思決定に活用できるインサイトを提供したりすることもできます。これにより、人手による単純作業が削減され、従業員はより付加価値の高い業務に集中できます。AIとRPAを組み合わせた活用により、イントラマートは「効率化」と「高度化」を両立させる強力な基盤として機能します。
intra-martを導入するメリット
intra-martは、単なるワークフローシステムにとどまらず、企業全体の業務基盤を支えるプラットフォームとして導入するメリットが多岐にわたります。日常業務の効率化や生産性向上はもちろんのこと、ローコード開発によるスピーディなアプリ開発、コスト削減、セキュリティ強化、将来的な拡張性など、企業の成長とDX推進を支える要素が網羅されています。これらの特長は大企業のみならず、中堅・中小企業にとっても大きな価値をもたらします。
ここでは、intra-martを導入する5つの代表的なメリットを解説します。
業務効率化と生産性向上
intra-martを導入する最大のメリットは、業務効率化による生産性向上です。ワークフロー管理機能により、これまで紙やメールで行われていた申請・承認業務をデジタル化し、業務プロセスを可視化・自動化できます。承認ルートの複雑な条件分岐にも柔軟に対応でき、進捗がリアルタイムに確認できるため、意思決定のスピードも飛躍的に向上します。
さらに、部門横断的な情報共有が促進され、属人化していた業務の標準化も可能です。結果として、従業員が単純作業に費やす時間が削減され、より付加価値の高い業務や戦略的な取り組みに注力できる環境が整います。
開発スピードの向上
イントラマートのローコード開発基盤は、アプリケーション開発のスピードを大幅に高めます。従来、システム開発には専門的なプログラミング知識と長期間の開発期間が必要でしたが、イントラマートではGUIベースでの設計や部品の再利用により、迅速なアプリ構築が可能です。現場部門が自ら業務に必要なアプリを作成できるため、IT部門への依存度も軽減されます。
これにより、急速に変化する市場環境や社内ニーズに柔軟に対応でき、DX推進のスピードを加速させます。短期間でアプリをリリースできる点は、競争力維持に直結する重要なメリットといえるでしょう。
コスト削減
イントラマートを導入することで、企業は大幅なコスト削減を実現できます。まず、申請書類のペーパーレス化により印刷費や保管コストを削減できるのはもちろん、承認スピードの向上により業務停滞による機会損失も減少します。
また、ローコード開発による内製化が可能になることで、外部ベンダーへの委託費やシステム開発コストを抑制できます。さらに、複数の業務システムを統合し、一元管理することで運用コストの最適化も可能です。これらの積み重ねにより、導入コストを上回る投資対効果(ROI)を短期間で得られる点が、多くの企業に選ばれる理由となっています。
セキュリティ強化
企業にとってセキュリティは最重要課題の一つです。イントラマートはアクセス権限管理やログ監査機能を備え、誰がいつどの情報にアクセスしたかを明確に記録できます。これにより、不正アクセスや情報漏洩リスクを低減でき、内部統制やコンプライアンス強化にもつながります。
さらに、クラウド・オンプレミス双方に対応しており、企業のポリシーやセキュリティ要件に応じた環境構築が可能です。情報セキュリティの国際基準に準拠した仕組みを持つことで、取引先や顧客に対しても高い信頼性を示すことができ、安心してビジネスを展開できます。
拡張性と将来性
イントラマートは高い拡張性を備えており、将来的な業務拡大や変化に柔軟に対応できます。ERPやCRMなどの基幹システムとの連携はもちろん、APIを活用した外部アプリとの接続も容易で、企業独自のIT環境に適合させることが可能です。
さらに、AIやRPAとの連携により、業務自動化の範囲を拡張し、将来的なDXの深化にも対応します。また、ローコード開発によって継続的に新しいアプリを追加できるため、環境変化や制度改正にも迅速に対応可能です。イントラマートは単なる現在の課題解決にとどまらず、将来を見据えた企業の成長基盤として長期的な価値を提供します。
他社のローコード開発プラットフォームとの比較
ローコード開発プラットフォームは近年急速に普及しており、企業がDXを推進する上で欠かせない存在となっています。その中で「intra-mart」は、ワークフロー基盤と業務システム統合に強みを持つ国産のプラットフォームとして高い評価を得ています。一方で、Microsoftの「Power Platform」、OutSystemsの「OutSystems」、サイボウズの「kintone」といった他社製品も広く導入されています。
Power PlatformはOffice 365やTeamsとの親和性が高く、グローバル規模での利用が多い点が特徴です。OutSystemsは高度なアプリ開発機能を備え、複雑なシステム構築にも対応できるエンタープライズ志向のプラットフォームです。kintoneは直感的なUIとシンプルな操作性で中小企業に人気があり、業務アプリを迅速に立ち上げられる点が強みです。イントラマートはこれらと比較して、ワークフローとシステム統合を中心とした「業務プロセス全体の最適化」に特化しているのが最大の差別化ポイントといえるでしょう。
| intra-mart | Power Platform | OutSystems | kintone | |
| 開発元 | NTTデータイントラマート(日本) | Microsoft(米国) | OutSystems(ポルトガル発) | サイボウズ(日本) |
| 強み | ワークフロー管理/基幹システム連携に強い | Office製品やTeamsとの高い親和性 | 複雑なアプリ開発に対応/エンタープライズ向け | 直感的UI/中小企業向けに導入容易 |
| 導入規模 | 大企業から中堅企業まで幅広い | グローバル規模の大企業中心 | 大規模システムを必要とする企業 | 中小企業・部門単位での導入が中心 |
| 主な用途 | 業務プロセス全体の最適化 | データ分析/業務自動化 | 高度な業務アプリ構築 | 部門業務の効率化/小規模DX |
intra-martの活用事例3選
intra-martは、国内外7,000社以上に導入され、幅広い業種・業態で業務改革やDX推進を支えています。特に、基幹システムとの連携やワークフロー管理に強みを持つため、大企業から中堅企業まで幅広く活用されているのが特徴です。
ここでは、実際にintra-martを導入し、業務効率化や業務プロセス改革を実現した代表的な3社の事例を紹介します。製造業、通信業、建設業といった異なるフィールドでの活用を知ることで、イントラマートが持つ柔軟性と拡張性を具体的に理解できるでしょう。
東ソー情報システム株式会社

東ソー情報システム株式会社では、グループ全体の情報基盤としてintra-martを導入しました。従来、部門ごとに異なるシステムを利用していたため、業務プロセスが複雑化し、情報の一元管理が難しいという課題を抱えていました。イントラマートを導入することで、申請・承認フローの統一や、情報の横断的な検索・活用が可能になり、グループ全体での業務効率化を実現。さらに、ローコード開発機能を活用することで、各部門のニーズに応じた業務アプリをスピーディに開発できるようになりました。
その結果、グループ会社間での情報共有が円滑になり、全体最適を意識した経営判断が可能になった点が大きな効果として挙げられています。
参照元:東ソー情報システム株式会社
株式会社オプテージ

株式会社オプテージは、関西を中心に通信サービスを提供する企業で、業務効率化とサービス品質向上を目的にintra-martを導入しました。従来の業務フローは紙やメールに依存しており、承認作業に時間がかかることが課題でした。イントラマートを導入後は、ワークフロー管理機能により承認プロセスを電子化し、進捗をリアルタイムで確認できるようになったことで、業務スピードが大幅に向上。加えて、顧客対応に関するデータを一元管理できる仕組みを整えたことで、社員が迅速かつ正確に顧客対応できる環境が整いました。
これにより、内部業務の効率化と顧客満足度向上を同時に実現し、通信サービス企業としての競争力を強化する結果につながっています。
参照元:株式会社オプテージ
エクシオグループ株式会社

エクシオグループ株式会社では、建設業界特有の多様な業務フローを標準化・効率化するためにintra-martを導入しました。従来は部門やプロジェクトごとに異なるプロセスが存在し、管理の煩雑さや情報共有の遅れが問題となっていました。イントラマートのワークフロー基盤を活用することで、社内の申請・承認プロセスを統一し、どの部門でも共通のルールで業務が進められる環境を構築。さらに、モバイルからの承認や外部システムとの連携により、現場作業員も含めた全社的な業務効率化を実現しました。
その結果、業務の属人化が解消され、品質・コスト・納期のバランスを保ちながら事業を推進できる体制が整ったことが大きな成果となっています。
参照元:エクシオグループ株式会社
HBLABとイントラマートの協業:ベトナムCoEセンター設立イベント

2025年2月7日、株式会社エイチビーラボは、株式会社NTTデータイントラマートおよびアキラ株式会社が主催した「イントラマート ベトナムCoEセンター」設立イベントに参加しました。
このCoEセンターは、エンタープライズ・ローコードプラットフォーム「intra-mart®」を活用した開発スキルを持つエンジニアの育成を目的としています。具体的には、ベトナム語による研修プログラムや認定試験を通じて、ローコード開発、生成AI活用、オフショア開発に不可欠な品質スキルを習得したエンジニア1,000名の育成を目指しています。
HBLABは本イベントを通じて、イントラマートとの協業強化およびDX推進を支える人材育成に積極的に貢献していきます。今後もイントラマートとのパートナーシップを通じ、日本企業に最適なローコード開発・オフショアソリューションを提供してまいります。
参考リンク:
エイチビーラボ、最初の7社のパートナーとしてベトナムにイントラマートCoEセンター設立イベントに参加
まとめ
intra-mart(イントラマート)は、ワークフロー管理やローコード開発、基幹システム連携を強みに、多くの企業で業務効率化やDX推進を実現してきた国産のプラットフォームです。本記事では、その機能や導入メリット、他社製品との比較、具体的な活用事例を紹介しました。自社に合った形でイントラマートを導入することで、生産性向上やコスト削減、将来を見据えた柔軟なシステム基盤を構築できます。
HBLABでは、イントラマートをはじめとするローコード開発やシステム連携の豊富な実績を持ち、お客様の課題解決に最適なソリューションを提供しています。DX推進や業務改革を加速させたいとお考えの方は、ぜひHBLABにご相談ください。
-1-1024x538.png)
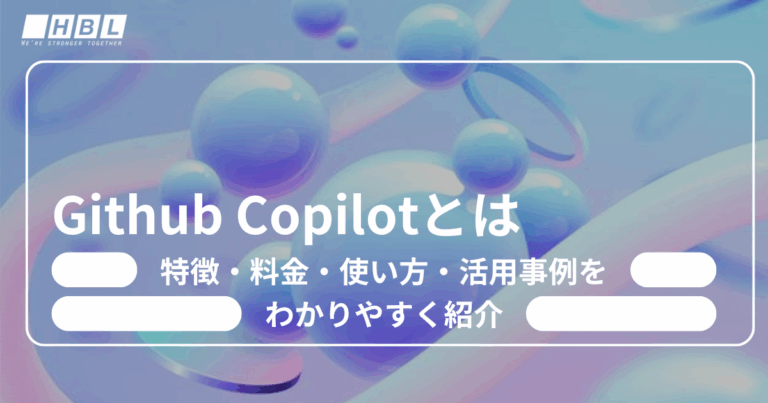

とは-768x403.webp)

