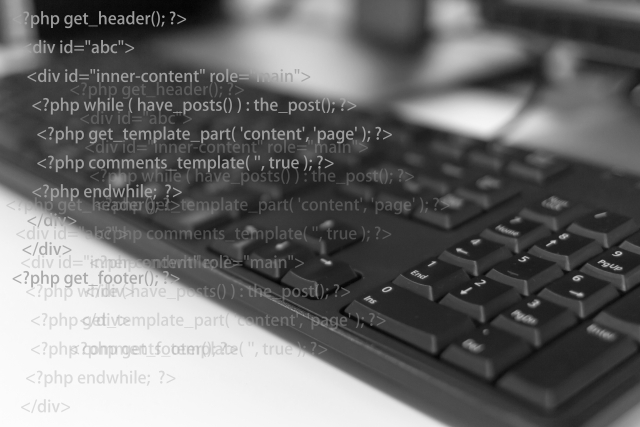Reactとは?主な特徴や開発で導入するメリット・デメリットを解説
JavaScriptはわかるものの、JavaScriptのライブラリは詳しく知らないという方は多いのではないでしょうか。本記事ではJavaScriptライブラリであるReactのメリット・デメリットや、特徴について解説します。 Reactとは? ReactはFacebookが開発したJavaScriptのライブラリです。 主にWebサイトのUIパーツを構築するために使われています。多くのWebサービスがReactによって開発されており、JavaScriptライブラリの中でも知名度が高いです。 そもそもJavaScriptとは? JavaScriptはWebアプリ開発で使われるプログラミング言語です。 Webアプリは、Webページを作成する処理を行うバックエンドと、表示後のWebベージを動かす処理を行うフロントエンドの2種類のプログラムによって構成されています。JavaScriptはフロントエンドで活躍することが多いです。 JavaScriptを使うことでWebページにアニメーションやスライドショーを設置したり、ユーザーがフォームに書き込んだ内容のチェックを行ったりすることができます。SNSやECサイトなどのWebアプリにはJavaScriptは必要不可欠と言えるでしょう。 JavaScriptは長年活躍し続けている言語です。そのため、有志の方が作成したライブラリ・フレームワークが数多くあります。 ライブラリとは? ライブラリとは、開発に必要な機能があらかじめパッケージ化されたもののことです。ライブラリをインストールして自分のプログラムから読み込ませることができます。 ライブラリを利用すれば自分でコードを書かなくて良いため、開発コストを下げることが可能です。また、スキルレベルが低くてもライブラリを活用すれば、ある程度は本格的なアプリが作れてしまいます。 Reactはライブラリの1種類です。Reactはフレームワークであると解説しているサイトもありますが、公式サイトにはライブラリであると記載されています。 フレームワークとは開発時に枠組みとして使うものです。ライブラリ同様必要な機能をパッケージ化していますが、ライブラリは1部の機能のみ提供するのに対し、フレームワークは開発に必要な機能を一通り提供します。 […]
Reactとは?主な特徴や開発で導入するメリット・デメリットを解説 続きを読む